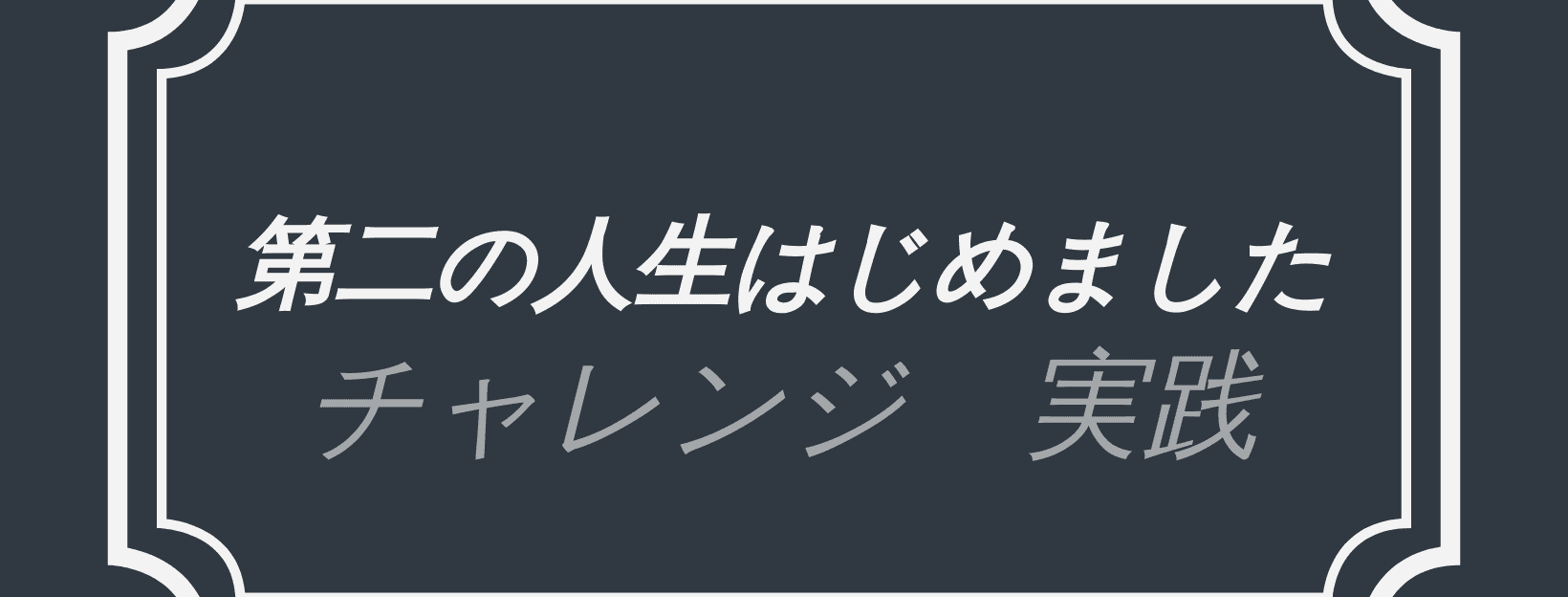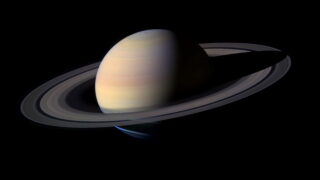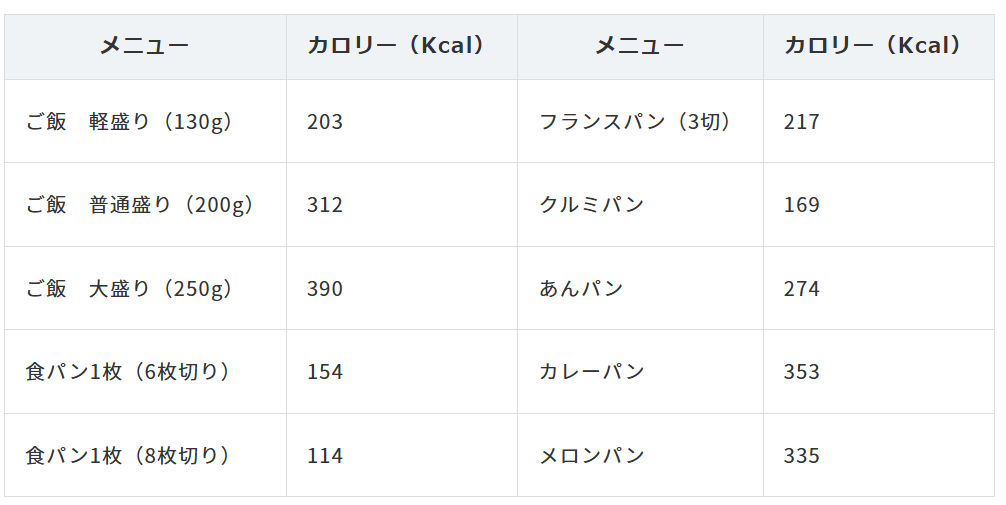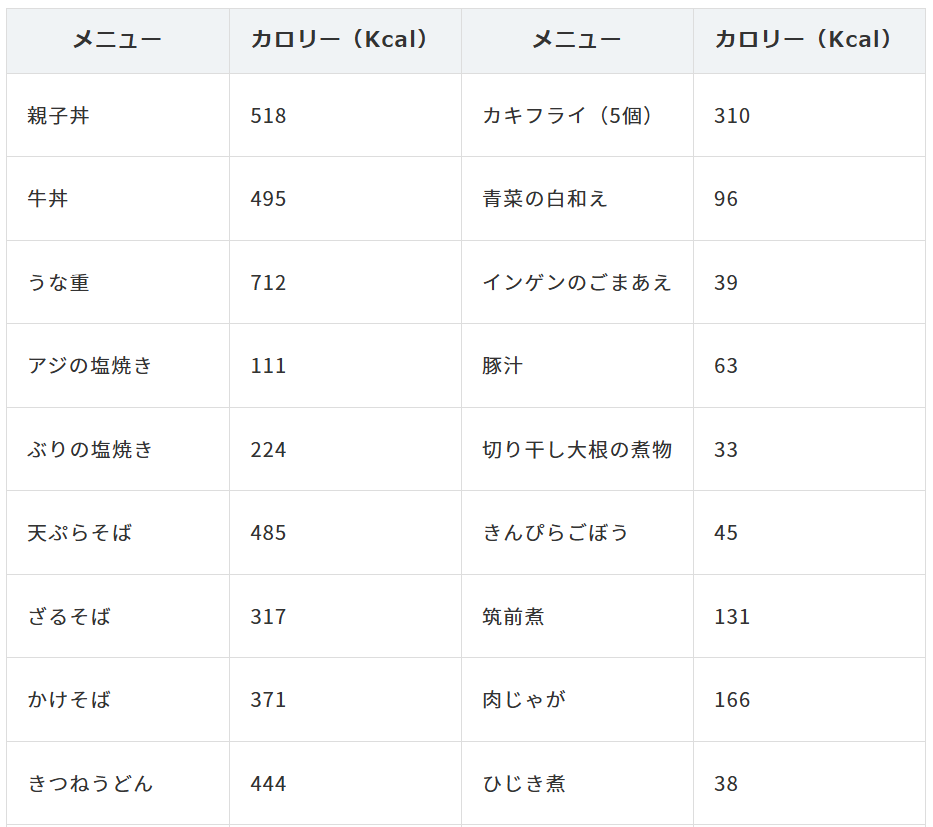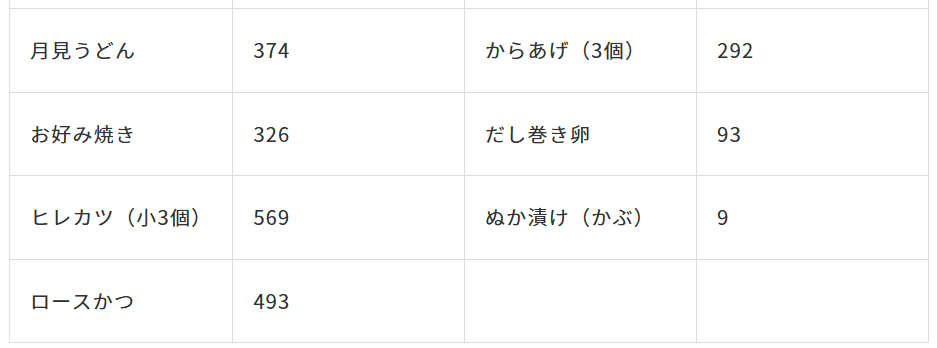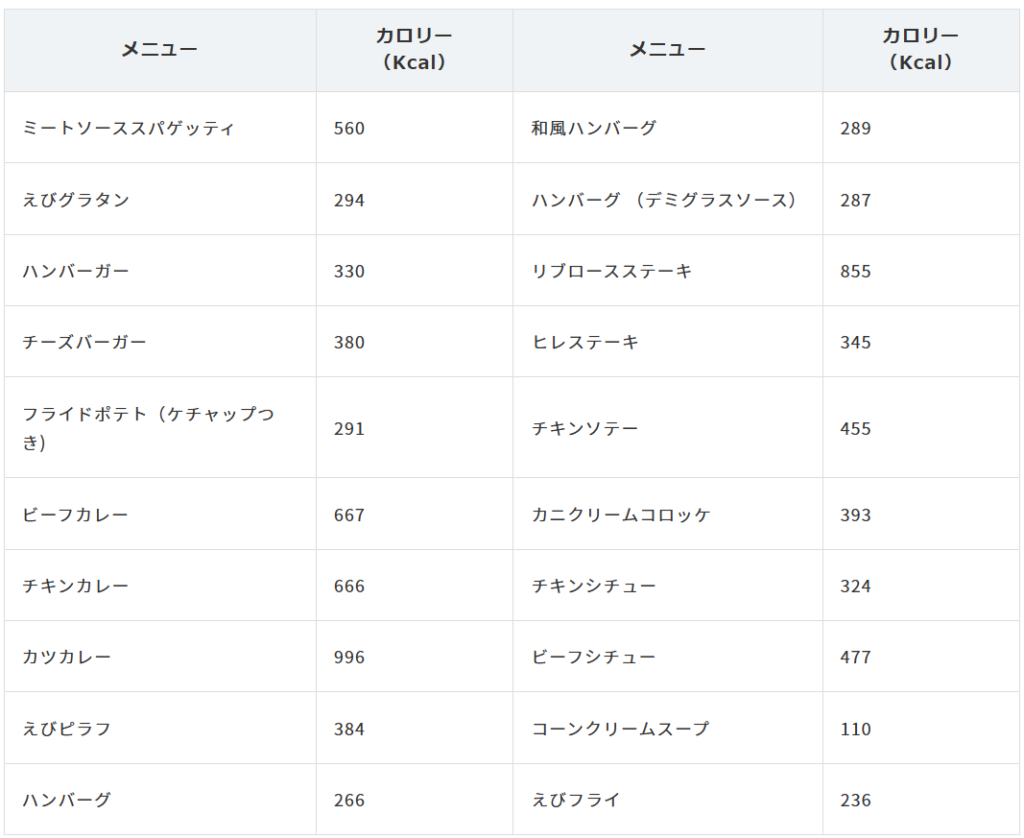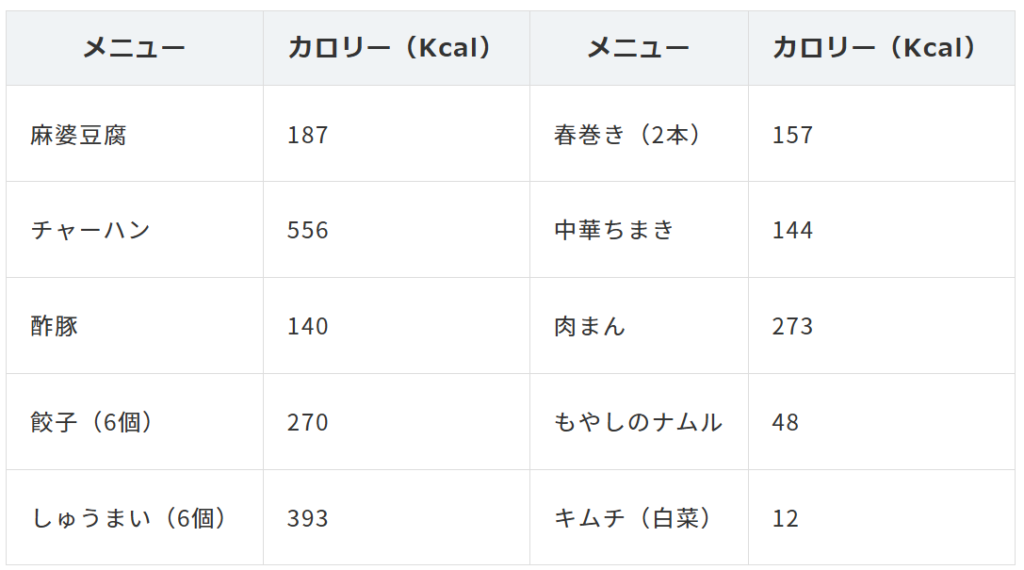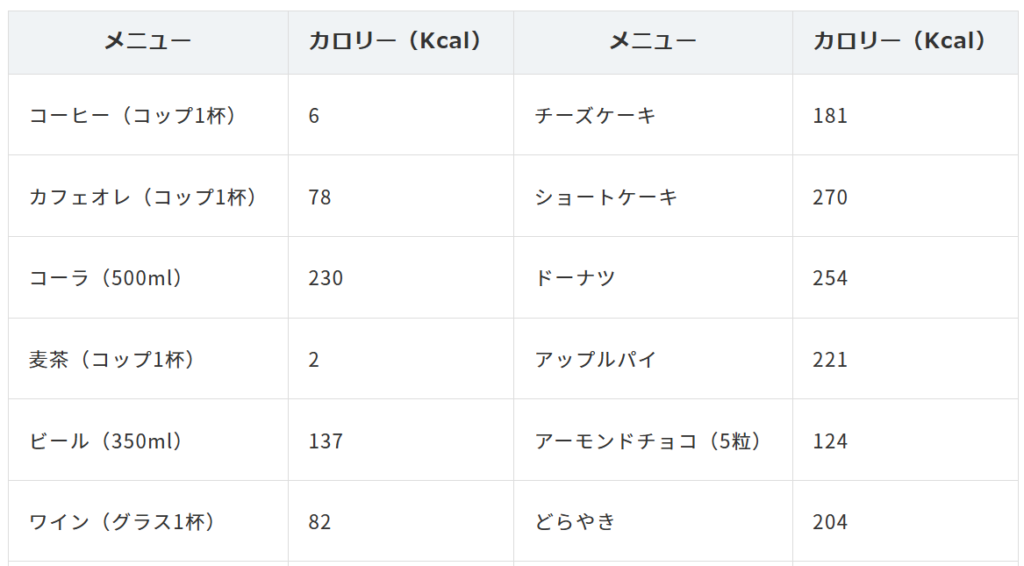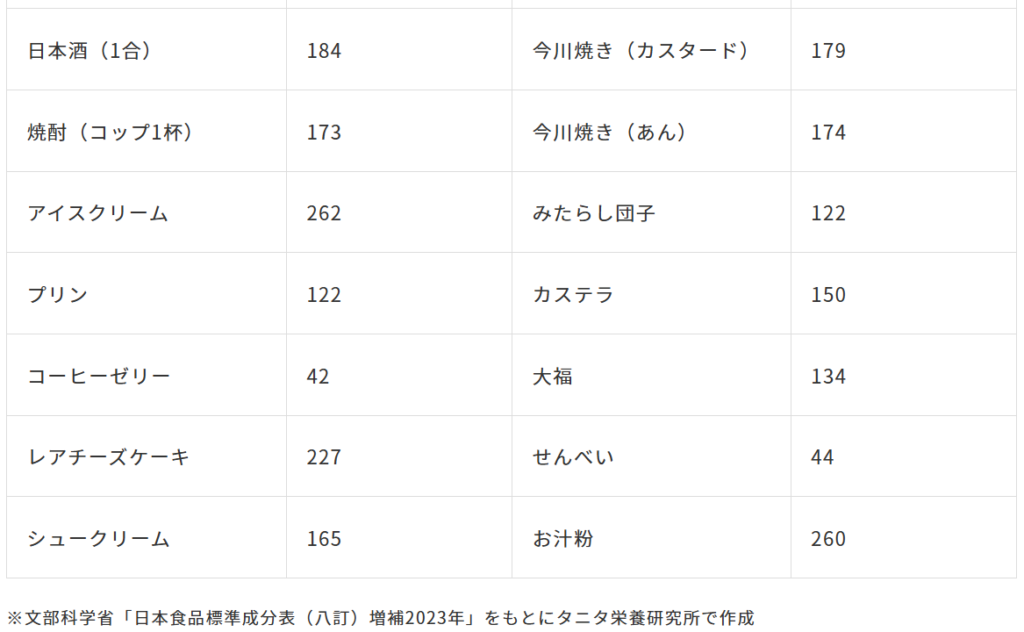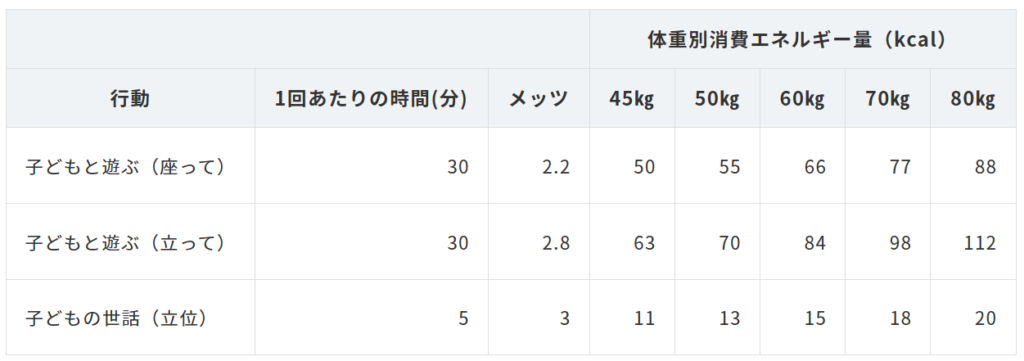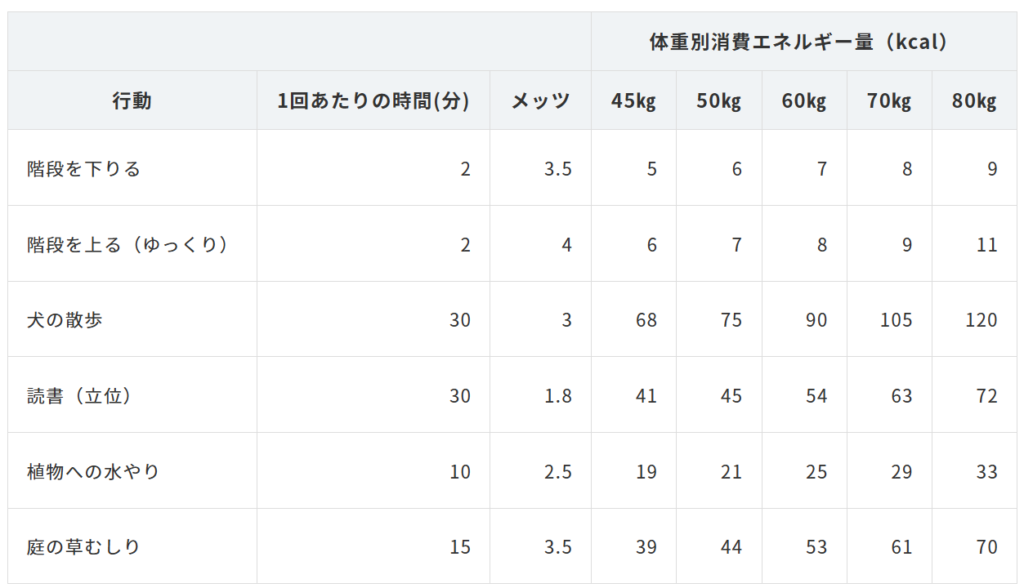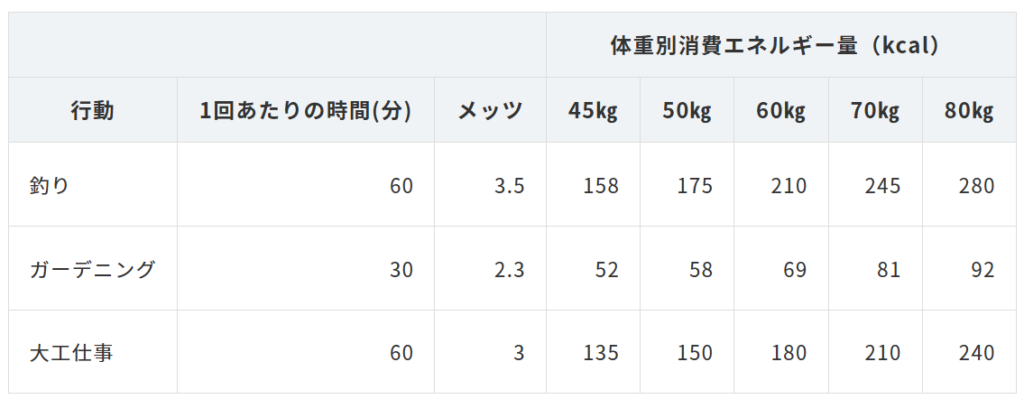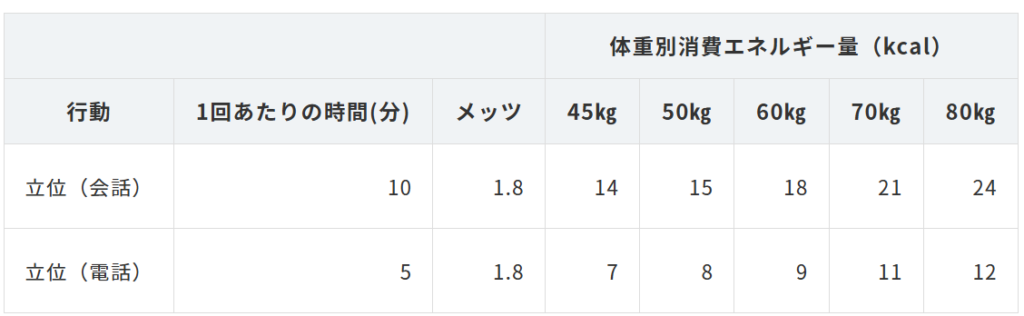定年を迎え、活動量が減ると、カロリーの過剰摂取や運動不足により、体重が増えてしまう。
これが「高血圧」や「高血糖」「高コレステロール」といった、健康リスクにつながることは、多くの人が理解している。
しかし、「健康の大切さを実感するのは、病気をしてから」という話をよく耳にする。
そうならないよう、「ダイエット」を始める人もいるが、「なかなか効果が出ない」と感じ、途中で諦めてしまうケースが多い。
ここでは、ダイエットを始めてどの程度の期間で、どのような変化が現れるのか、途中で挫折する原因や心理状態を分析し、無理なく継続し、リバウンドを防ぐ方法について見ていきたい。
ダイエットの効果が出るまでの期間と体の変化
「ダイエット」の効果は、すぐには現れない。
多くの人は「1週間で劇的に痩せる」と期待するが、現実は異なる。
「ダイエット」には段階があり、それぞれの期間で、体にどのような変化が起こるのかを、知っておくことが重要である。
1. 「初期(1週間〜2週間)」の体の変化と心理状態
「ダイエット」を始めたばかりの1週間〜2週間は、体が変化し始める大切な時期である。
しかし、劇的な変化が起こるわけではなく、むしろ不安やストレスを感じやすい時期でもある。
この期間で、急激に体重が減ることがあるが、多くは「水分」と「筋肉のグリコーゲン(糖質の貯蔵エネルギー)」が減った結果である。
脂肪が減るわけではないので、ここで停滞しすることが特徴である。
ポイント:体重が減りやすいが脂肪は落ちていない
「ダイエット」を始めると、まず水分と筋肉内のグリコーゲンが減るため、急に体重が落ちることがある。
しかし、これは脂肪が減ったわけではなく、体内の一時的な変化にすぎない。
この時点で「簡単に痩せる」と思い込むと、後の停滞期で挫折しやすい。
吾輩も、2週間程度で3kgほど体重が減ったので、意外と簡単に減るもんだなと思っていた。
① 体の変化(1週間〜2週間)
✅ 最初に減るのは「水分」
「ダイエット」を始めると、最初に減るのは脂肪ではなく水分である。
特に、炭水化物の摂取を控えると、体内のグリコーゲン(エネルギー源)が減り、それに結びついていた水分も排出される。
そのため、最初の1週間で1〜2kgくらい落ちることがある。
✅ むくみが取れ、少しスッキリする
塩分の摂取量が減ると、水分の滞留が解消され、顔や足のむくみが取れることがある。
そのため、「なんとなくスッキリした感じ」がすることも。
✅ 腸内環境が改善し、便通が良くなることも
食物繊維の多い食事や水分摂取を意識すると、腸の動きが活発になり、便秘が解消されることもある。
逆に、食事の変化により一時的に便秘になる人もいる。
✅ 体脂肪はまだ大きく減らない
脂肪燃焼が本格化するのは、3〜4週間目以降であり、最初の2週間では、体脂肪は大きく減らない。
そのため、体重計の数字だけに頼ると、「全然痩せていない」と思いやすい。
② 心理状態(1週間〜2週間)
ポイント:最初はやる気が高いが、次第に焦りや不安が出る。
✅ 1〜3日目:「よし、頑張るぞ!」
「ダイエット」を始めたばかりの頃は、モチベーションが最高潮。
「絶対に痩せる!」と決意し、食事や運動に気を使う。
✅ 4〜7日目:「少し痩せたかも?」
水分が抜け、1kgほど体重が減ることもあるため、「思ったより簡単かも」と感じる。
しかし、まだ見た目の変化はほとんどないため、「本当に効果が出るのかな?」と不安になり始める。
✅ 8〜14日目:「全然変わらない…」
最初に減った水分の影響が落ち着き、体重が停滞しやすい時期。
「あれ?最初は減ったのに…」と感じ、焦りや疑いが出てくる。
また、食事制限や運動の習慣がストレスになり、「こんなに頑張っているのに報われない」とモチベーションが低下する。
③ ダイエット初期に挫折しないための対策
ポイント1:「最初は水分が減るだけ」と理解しておく
この時期に大事なのは、「まだ脂肪は大きく減らない時期」だと知っておくこと。
「脂肪燃焼はこれから」という意識を持つことで、不安を減らせる。
吾輩も、このことを知っていたおかげで、挫折せず次ぎのステップに進むことが出来た。
ポイント2:体重だけでなく、体調や見た目の変化もチェック
体重だけに注目すると、減らなくなったときに焦りやすい。
そのため、「むくみが取れた」「お腹の張りが減った」「便通が良くなった」などの変化も評価し、ポジティブな面に目を向ける。
ポイント3:途中でやめないために、小さな成功体験を積む
「ダイエット」初期は、「とにかく続けること」が最も大事。
そのため、次のような小さな目標を設定すると良い。
- 「1週間続けたら、好きな本を買う」
- 「10日間達成したら、おしゃれなカフェでコーヒーを飲む」
- 「2週間続けたら、新しい運動ウェアを買う」
「ここまで頑張ったから、もう少し続けてみよう」と思える仕組みを作ることが、継続のカギになる。
④ 初期(1週間〜2週間)で覚えておくべきこと
✅ 最初に減るのは脂肪ではなく水分(1〜2kg減ることも)
✅ むくみが取れ、少しスッキリした感じがする
✅ 体脂肪はまだ大きく減らないので、体重だけで判断しない
✅ 1週間を過ぎるとモチベーションが低下しやすい
✅ 小さな目標を作り、途中でやめない仕組みを作る
「ダイエット初期は不安になりやすい時期」と知っておくだけでも、挫折を防ぐことができる。
1〜2週間目は「まだ準備期間」と捉え、焦らずコツコツ続けることが大切である。
2. 「停滞期(2週間〜1ヶ月)」の体の変化と心理状態
「ダイエット」を始めて2週間〜1ヶ月が経つと、多くの人が「停滞期」に入る。
停滞期とは、体が減量に適応し、体重が減りにくくなる時期のことである。
この時期は「努力しているのに痩せない…」と最も挫折しやすい時期でもある。
ここで多くの人が「効果がない!」と諦めてしまいがち。
これは、体が省エネモードになり、エネルギー消費を抑えている状態である。
「ダイエット」では、よくある現象なので、長期的な視点を持つことが重要だ。
ポイント:体が変化に慣れ、体重が落ちにくくなる(ホメオスタシスの働き)
この時期になると、体は「飢餓状態」に適応し、エネルギー消費を抑えるようになる。
これをホメオスタシス(恒常性維持機能)という。
ここで「努力しているのに痩せない」と焦ると、モチベーションが下がりやすい。
しかし、これは正常な過程であり、「ダイエット」を続けることで再び体重が減り始める。
ホメオスタシス(恒常性維持機能)
ホメオスタシスは、生態恒常性と呼ばれる概念である。
生態は何か変化が起こると、それを元の状態に戻そうとするために、様々な変化が生じるということである。
例えば、体温が下がると鳥肌になり体温の低下を防いだり、体を震えさせて強制的に運動を起こして体温を上げるなど。
このような、安定した状態を保つために、内分泌系、自律神経系、免疫系などに変化が起きる機能をホメオスタシスという。
ホメオスタシスは生命活動の基本であり、これが正常に機能しているから生態は命を維持することが出来る。
ホメオスタシスの機能は先ほども述べたように内分泌系、自律神経系、免疫系である。
ストレスや環境変化によってホメオスタシスが損なわれると、体がだるくなったり、心臓や筋肉の機能に影響したり、細菌などに弱くなってしまう。
引用元:安全衛生マネジメント協会 ホメオスタシスとは
① 体の変化(2週間〜1ヶ月)
✅ 体が「省エネモード」に入る(ホメオスタシス効果)
「ダイエット」を始めると、摂取カロリーが減り、体は「エネルギー不足」と判断する。
すると、基礎代謝を下げて、消費カロリーを抑えようとする。
これが「ホメオスタシス(生体恒常性)」の働きであり、停滞期の主な原因である。
✅ 体重がほとんど変わらなくなる(または微増することも)
初期(1〜2週間目)は水分が抜けて体重が減ったが、この時期になると水分量の変動が落ち着き、体脂肪の減少スピードも遅くなる。
その結果、体重が停滞する、または微増することがある。
吾輩も、この時期は、体重減少が停滞していたので、「ホメオスタシス」の働きを知っていたことで、頑張ることが出来ている。
知識が有るか無いかで、その後の結果に影響を及ぼすと思うと、情報収集の重要さがわかる。
✅ 筋肉が分解されやすくなる
食事制限をしすぎると、エネルギー不足を補うために、筋肉が分解されやすくなる。
そのため、筋肉量が減ることで基礎代謝もさらに落ち、ますます痩せにくい体質になる。
✅ 見た目は引き締まり始める
体重の変化がなくても、筋肉がついてきたり、脂肪の分布が変わることで、ウエスト周りや顔が引き締まることがある。
体重よりも「見た目の変化」に注目すると良い。
吾輩も、この時期は、最初の1週間程度でガクッと体重が3kg減った後は、ほとんど変化が無くなった。
しかし、体脂肪率は、25%から23%に減少していた。
② 心理状態(2週間〜1ヶ月)
ポイント1:「頑張っているのに痩せない…」という焦りや不安
✅ 体重が減らない → モチベーション低下
この時期、多くの人が「なぜ痩せないのか?」と不安になる。
特に、最初の1〜2週間で順調に体重が落ちた人ほど、停滞期で大きなストレスを感じる。
吾輩も、まさにこの思いで、ストレスを感じている。
✅ 「食事制限や運動が無駄だったのか?」と疑い始める
「頑張っているのに効果がないなら、もうやめようかな…」と感じることが多くなる。
この心理状態が、「ダイエット」を挫折する大きな要因となる。
ポイント2:「もう少し食べてもいいかも…」という誘惑
✅ 停滞期が続くと「食べても変わらない」という気持ちが出る
体重が減らないと、「少しくらい食べても同じでは?」という気持ちが出てくる。
特に、ストレスが溜まると食べたくなるため、ドカ食いのリスクが高まる。
吾輩も、食べる量を控えているので、ストレスがたまっていて、アイス(カロリー300kcal以上)を食べたいが、我慢するのがつらい。
✅ 「こんなに頑張る必要ある?」と、気の緩みが出る
「もうちょっと楽な方法でいいんじゃないか?」と考え始め、運動をサボったり、間食を増やしたりする人が増える。
ポイント3:「もうやめようかな…」という諦めの気持ち
✅ 「ダイエット向いてないかも…」と自己否定しやすい
努力しているのに結果が出ないと、「やっぱり私はダイエットに向いていないんだ」とネガティブになることがある。
吾輩も、最初の1週間の様に体重が減らなくなったので、この停滞期には、「何故減らないんだ」「ダイエットには向いていないかも」と思い悩んでいた。
✅ 「リバウンドするなら今のうちに食べよう」と思う人も
「ダイエット」を諦めかけると、「どうせリバウンドするなら、今のうちに食べよう」と暴食してしまうケースもある。
③ 停滞期を乗り越えるための対策
ポイント1:「停滞期は誰にでも起こる」と理解する
まず、「停滞期は、正常な生理反応」と知ることが大切である。
停滞期は「体が変化に適応している証拠」なので、この時期を乗り越えれば、また体重は落ち始める。
✅ 「あと1〜2週間我慢すれば、また減る」と考える
停滞期は、通常1〜3週間程度で終わることが多い。
ここでやめてしまうのはもったいない。
ポイント2:体重ではなく、見た目の変化をチェックする
✅ 「ウエストや顔が引き締まったか?」を確認する
体重が変わらなくても、鏡で見ると体のラインがスッキリしていることがある。
写真を撮って比較すると、変化を実感しやすい。
✅ 「体脂肪率」や「ウエストサイズ」も測る
体重よりも、体脂肪率やウエストのサイズを指標にすると、変化を感じやすい。
吾輩も、ダイエットアプリを活用し、体重の他に体脂肪率を記録している。
ポイント3:「チートデイ」を取り入れる
✅ 1日だけ好きなものを食べて、代謝を活性化する
極端な食事制限を続けると、体が飢餓状態になり、エネルギー消費が低下する。
そこで、チートデイ(1日だけカロリーを多めに摂る日)を設けると、代謝が回復し、脂肪燃焼が促進されることがある。
✅ ポイントは「適度に食べること」
「チートデイだから」と暴飲暴食すると逆効果なので、ご飯やパンなどの炭水化物を少し増やす程度が理想的である。
ポイント4:「あと1週間だけ頑張る」と考える
✅ 「1ヶ月続けよう」と思うと辛いが、「あと1週間」と考えると楽になる
停滞期は心理的に苦しいが、短期目標を設定することで乗り越えやすい。
④ 停滞期(2週間〜1ヶ月)で覚えておくべきこと
✅ 停滞期は、「ホメオスタシス(生体の適応反応)」であり、誰にでも起こる
✅ 体重が減らなくても、見た目は引き締まることがある
✅ 「あと1〜2週間で抜ける」と考え、途中でやめない
✅ チートデイを活用し、代謝をリセットするのも有効
✅ 短期目標を立て、「あと1週間だけ続けよう」と思う
停滞期は「ダイエット」の「試練」だが、乗り越えれば再び減量が進む。
ここで諦めずに継続できるかどうかが、「成功する人」と「失敗する人」の分かれ道である。
3. 「脂肪燃焼期(1ヶ月〜3ヶ月)」の体の変化と心理状態
「ダイエット」を始めて1ヶ月を過ぎると、停滞期を抜けて「脂肪燃焼期」に入る。
この時期になると、体がエネルギー消費の仕組みに適応し、脂肪が本格的に燃焼し始める。
体が新しい生活習慣に適応し始め、徐々に脂肪が落ちてくる時期であり、体重の変化が少なくても、見た目やウエストサイズが変わってくる。
体の変化がより明確に現れ、「ダイエット」の成果を実感しやすくなるが、モチベーションの維持がカギとなる時期でもある。
吾輩も、最初の1~2ヶ月の様に、体重の減少が鈍くなってきている。
このことで、モチベーションが落ちてきているのが現状だ。
特に、体が動きやすくなって、筋トレや少しハードな運動にチャレンジしようとして、逆に体重が増えてしまう事が、モチベーション低下の原因だ。
ポイント:体型の変化が現れる
ここから本格的に脂肪が燃え始める。
体重の減少が少なくても、ウエストや太ももなどのサイズが、変わることが多い。
この時期になると、周囲から「痩せた?」と言われるようになり、成果を実感しやすくなる。
① 体の変化(1ヶ月〜3ヶ月)
✅ 体重が安定して減少し始める
停滞期を抜けると、1週間で0.5〜1kg程度のペースで体重が減る人が多い。
個人差はあるが、1ヶ月で2〜4kgの減量が目安となる。
✅ 体脂肪がしっかり燃焼し、見た目が変化する
この時期は、体重の減少よりも体脂肪の燃焼が進むため、見た目の変化が大きい。
特に、お腹・太もも・顔の脂肪が落ちやすく、ウエストが細くなる人が増える。
吾輩は、体脂肪率も記録をしているが、一時体重が増えても体脂肪率が減っているので、モチベーションをかろうじて維持することが出来ている。
✅ 筋肉がつき始め、基礎代謝が向上
運動を取り入れている場合、筋肉量が増え、基礎代謝が上がる。
その結果、食べても太りにくい体質になり、リバウンドしにくくなる。
✅ 食欲や間食のコントロールがしやすくなる
この時期になると、血糖値の乱高下が少なくなり、過食や間食の欲求が減ることが多い。
「ダイエット」を始めたばかりの頃よりも、食事のコントロールが楽になってくる。
吾輩も、ダイエットを始めたころは、食欲の方が勝り、食事の量をコントロールが難しかったが、3ヶ月が経つと、食事量のコントロールが楽になった。
そう実感できる。
✅ 運動が習慣化し、体力が向上する
最初はきつかった運動も、継続することで慣れてきて、楽に感じるようになる。
体力がつき、日常生活でも疲れにくくなるのを実感できる。
吾輩も、ウォーキングしていても息切れがしなくなったり、歩く速度が速くなったり、歩幅が広くなったりしていて、体力がついたように感じている。
しかし、ハードな運動後には、体重が増えていることが多く、水分が体に残っている「むくみ」の様な感覚がある。
これには、以下の様な原因がある。
ハードな運動や筋トレで、体重が増える主な理由は、筋肉量の増加と体内水分量の変化によるものとされ、その量は、「1kg程度」とされ、吾輩の場合は、0.7kgである。
なぜ増えるのかについては、「単純に筋肉量が増える」「筋肉が修復される過程で一時的に水分が蓄えられる」、などがあげられる。
筋肉が増えることで、筋肉内のグリコーゲンが増え、そのグリコーゲンが水分と結びつきやすいため、とされる。
この様に、一時的にハードな運動や筋トレで体重が増えることは、ポジティブな変化として捉える事が大切で、これは、見た目が引き締まり体脂肪が減っている証拠である。
事実、吾輩の場合も、体重は0.7kg増えたが、体脂肪率は減っている。
② 心理状態(1ヶ月〜3ヶ月)
ポイント1:「ダイエットが成功している!」という達成感
✅ 体重が落ち、見た目が変わることで自信がつく
「鏡を見るのが楽しくなった!」「服がゆるくなった!」など、「ダイエット」の成果を実感し、モチベーションが高まる時期である。
✅ 「続ければもっと痩せられる」と前向きになる
この時期になると、「思ったより順調だから、もっと頑張ろう!」と、ポジティブに捉える人が増える。
ポイント2:「まだ目標まで遠い…」と焦る気持ち
✅ 最初に比べると減量スピードが遅く感じる
最初の1〜2週間は急激に体重が減ったが、この時期になるとゆるやかな減少になるため、「思ったより痩せない」と感じる人もいる。
吾輩は、最初の1~2ヶ月の間は、2kgほど1ヶ月で体重が減っていたが、3ヶ月目には、ほとんど変化が見られなくなった。
3か月目の体重変化は「ゼロ」だ。
しかし、体脂肪率は、25.0%から20.5%と、順調に減ってきている。
体重だけ記録していると、体の変化に気づきにくくなり、モチベ―ションの低下につながる要因となりやすい。
ウエストや、腰回りなど体の部位を測定しておくと体の変化を感じやすくなる。
✅ 「あと◯kg痩せるにはどれくらいかかる?」と計算し始める
目標までの道のりを考え、「このペースだとあと何ヶ月かかるのか?」と、先のことを気にする人が増える。
吾輩も、体重の減りが遅くなってきてからは、「あと何キロ減らさなくちゃいけない」と追い込まれるような感覚が強くなっている。
ポイント3:「もうこれくらいでいいかな?」と気の緩みが出る
✅ 「ダイエット成功したし、そろそろ普通の生活に戻そうかな…」
目標を達成しきっていないのに、「ある程度痩せたから、もういいかも」と思い始める人もいる。
✅ リバウンドの危険がある時期
「少し食べても大丈夫かな?」「運動を休んでもいいかな?」と考え始めると、リバウンドのリスクが高まる。
ポイント4:「もっと筋肉をつけたい」「健康的な体になりたい」と意識が変わる
✅ 「痩せる」から「引き締める」へと意識が変わる
体重が減ると、単に痩せるだけでなく「もっと引き締めたい」「美しく痩せたい」と考える人が増える。
✅ 健康への意識が高まる
「リバウンドしないように、ずっと続けられる習慣を作ろう」と考えるようになる人も多い。
吾輩の場合は、これを一生続けなければならないのかと思うと、心配でしかない。
何をしたら良いか、まだ決められていない。
③ 脂肪燃焼期を乗り越えるための対策
ポイント1:目標を細かく設定し、「次のステップ」を決める
✅ 「◯kg減ったら、新しい服を買う」などの目標を作る
大きな目標だけでなく、「小さな成功体験」を積み重ねると、モチベーションが続きやすい。
✅ 「ダイエットのその先」を考える
「単に痩せるだけでなく、引き締まった体を目指す」「リバウンドしない習慣を作る」といった長期的な目標を持つのも効果的。
吾輩は、ウォーキングや筋トレを、これからズーット続けられるか不安だ。
ポイント2:チートデイやご褒美を適度に取り入れる
✅ 「週に1回は好きなものを食べる日を作る」
厳しすぎる「ダイエット」は、ストレスになりやすいので、適度に楽しみながら続ける工夫が必要。
✅ 「頑張った自分に何かご褒美をあげる」
例えば、体重が5kg減ったらマッサージに行く、新しい服を買うなど、ダイエット以外の楽しみを取り入れると続けやすい。
ポイント3:運動の質を上げて、より効果的に脂肪を燃やす
✅ 有酸素運動+筋トレを組み合わせる
脂肪燃焼を加速させるには、有酸素運動(ウォーキング・ランニング)だけでなく、筋トレを取り入れるのが効果的。
✅ 「楽しめる運動」を見つける
同じ運動を続けるのが辛くなったら、ダンス・ヨガ・水泳など、飽きない工夫をする。
④ 脂肪燃焼期(1ヶ月〜3ヶ月)で覚えておくべきこと
✅ 体脂肪が本格的に燃焼し、ウエストや顔が引き締まる
✅ 停滞期を抜け、体重がゆるやかに減る
✅ 「もっと頑張ろう」と感じる人と、「もう十分かな」と気が緩む人に分かれる
✅ ダイエットのその先(リバウンド防止・引き締め)を考え始める
✅ 適度にご褒美やチートデイを取り入れ、ストレスを溜めない
この時期を乗り越えれば、リバウンドしにくい体質が作られ、理想の体型を維持しやすくなる!
4. 「維持期(3ヶ月〜半年以上)」の体の変化と心理状態
「ダイエット」開始から3ヶ月以上が経過すると、「痩せること」から「理想の体型を維持すること」に意識が変わる時期に入る。
ここでは、減量期を乗り越えた人がリバウンドを防ぎながら、健康的な生活を習慣化できるかどうかがカギになる。
「ダイエット」が成功した後、元の食生活に戻すとリバウンドしやすくなる。
特に、急激に減らした体重ほど戻りやすいため、「ダイエットが終わった」という意識を持たず、継続可能な習慣を続けることが大事。
ポイント:リバウンドを防ぐ習慣づくり
「ダイエット」はゴールではなく、新しい生活習慣を身につけることが重要である。
短期間で痩せても、元の生活に戻せば体重も戻る。
リバウンドを防ぐためには、食事や運動を、無理なく続けられる形に調整することが必要だ。
① 体の変化(3ヶ月〜半年以上)
✅ 体重が安定し、急激な変動が少なくなる
この時期になると、体が現在の体重に慣れ、減量スピードがゆるやかになる。
脂肪の減少はあるが、「目に見えて痩せる」という実感は少なくなる。
✅ 体型の引き締まりが進む
筋トレや運動を継続していると、筋肉量が増え、引き締まった体型になる。
体脂肪率が下がることで、見た目の変化(お腹がへこむ、ウエストが細くなる、フェイスラインがシャープになるなど)が続く。
✅ 代謝が向上し、食べても太りにくくなる
継続的な運動や食事管理により、基礎代謝が上がり、リバウンドしにくい体質に変化する。
以前よりも食事量が増えても、太りにくい状態を維持できる人も多い。
✅ 肌や髪の状態が良くなる
栄養バランスの取れた食事と、適度な運動を続けることで、肌のハリやツヤが増し、髪の毛が健康的になる。
✅ 疲れにくくなり、健康レベルが向上する
運動習慣が定着すると、体力がつき、疲れにくい体になる。
さらに、睡眠の質が向上し、体調が安定する人が増える。
② 心理状態(3ヶ月〜半年以上)
ポイント1:「ダイエットが成功した!」という達成感と自信
✅ 「ここまで続けられた!」という満足感
長期間の努力の結果、理想の体型に近づき、「やればできる」という自信がつく。
✅ 周囲からの変化に気づかれ、嬉しくなる
「痩せたね!」「なんか引き締まったね」と言われることが増え、「ダイエット」の成果を実感できる。
✅ 「もう太りたくない!」と意識が変わる
ここまで頑張ったからこそ、「リバウンドしたくない」「この体型をキープしよう」という意識が強くなる。
ポイント2:「油断するとリバウンドするかも…」という不安
✅ 食事の管理をどこまで続けるか悩む
「ダイエット」中は食事制限をしていたが、「これからはどの程度気をつけるべきか?」と迷う人が多い。
✅ 「ちょっと食べすぎても大丈夫?」と心配になる
以前より食べる量を増やしても、体重が大きく変わらないことに気づきつつも、「このまま気を抜いたら元に戻るかも」と不安になることも。
ポイント3:「モチベーションが下がる」or「新たな目標が生まれる」
✅ 「ダイエットのゴールが見えたし、もういいかな…」と気が緩む
目標体重に達すると、「もうダイエットは終わりでいいかな」と考え、運動や食事管理をやめてしまう人も。
✅ 「次はもっと引き締めよう」「健康を維持しよう」と思う人も
一方で、「さらに体を引き締めたい!」「筋肉をつけて健康的な体になりたい!」と新たな目標を設定する人もいる。
ポイント4:「食べても大丈夫な体になった!」という安心感
✅ 「少しくらい食べても太らない!」という余裕
基礎代謝が上がると、以前よりも食べる量が増えても体重が安定しやすくなる。
✅ ストレスなく食事を楽しめるようになる
厳しい食事制限をしなくても、適度に好きなものを食べながら健康を維持できるようになる。
③ 維持期を乗り越えるための対策
ポイント1:「ダイエットの次の目標」を設定する
✅ 「引き締める」「健康的な体を作る」といった新たな目標を持つ
単に痩せるだけでなく、「筋肉をつけて理想のボディラインを作る」「健康的に長く動ける体を目指す」といった次の目標を持つと、リバウンド防止になる。
✅ スポーツや新しい運動を取り入れる
「ダイエット」目的で始めた運動も、楽しめるもの(登山・ヨガ・ダンス・水泳など)を見つけることで、自然と運動習慣が続きやすい。
ポイント2:リバウンドを防ぐために「ゆるいルール」を決める
✅ 「平日はヘルシーな食事、週末は少し自由に」
厳しいルールを作りすぎると続かないため、「週に1回は好きなものを食べてもOK」「食べすぎた翌日は調整する」などの柔軟なルールを作ると良い。
✅ 「運動ゼロの日を作らない」
たとえ激しい運動をしなくても、毎日ストレッチやウォーキングをすることで、習慣を途切れさせない。
ポイント3:体の変化を定期的にチェックする
✅ 体重よりも「見た目」「体脂肪率」を重視
体重計に乗るだけでなく、鏡で体のラインをチェックしたり、ウエストサイズを測る習慣をつけると、変化に気づきやすい。
✅ 月に1回「健康チェックの日」を作る
食事・運動・体調を振り返る日を決め、無理なく続けられているかを確認するのもおすすめ。
④ 維持期(3ヶ月〜半年以上)で覚えておくべきこと
✅ 体重は安定するが、見た目の引き締まりは続く
✅ リバウンドを防ぐための「習慣化」が重要
✅ 新たな目標を設定すると、モチベーションが維持しやすい
✅ 食事や運動を楽しめる方法を見つけると、無理なく継続できる
この時期を乗り越えれば、「ダイエット」が「一時的なもの」ではなく、「一生続けられる習慣」に変わる!
なぜ途中で諦めてしまうのか?失敗の原因と人の心理(心構え)
「ダイエット」は、「短期間で劇的に痩せるものではない」と理解することが、成功のカギとなる。
特に、停滞期を乗り越える精神力と、リバウンドしないための習慣化が重要である。
焦らず、「健康的なライフスタイル」として続ける意識を持てば、自然と理想の体型を維持できる!
「ダイエット」が続かない主な「失敗の原因」は、以下のような点があげられる。
1.失敗の原因
① 目標が曖昧、または高すぎる
「ダイエット」を始める際、「〇kg痩せたい」「スリムになりたい」と漠然とした目標を立てたり、「1か月で10kg減」など現実離れした目標を設定すると、途中で挫折しやすい。
適切な目標設定をすることで、モチベーションを維持し、無理なく「ダイエット」を継続できる。
「とにかく痩せたい」と思っても、具体的な目標がないと、モチベーションが続かない。
「1ヶ月で10kg痩せる!」などの、無理な目標は、挫折しやすい。
✅ 対策:目標設定の方法
- 具体的で現実的な目標を設定する
「何となく痩せたい」ではなく、明確で達成可能な目標を決めることが、重要である。
▶ SMARTの法則で目標を立てる
目標設定には、「SMARTの法則」が有効である。
✔S(Specific):具体的に →「体重を〇kg減らす」
✔M(Measurable):測定可能に →「1か月で1kg減」など
✔A(Achievable):達成可能に → 無理のない範囲で設定する
✔R(Relevant):現実的に → 年齢・生活習慣に合った目標を立てる
✔T(Time-bound):期限を決める →「〇か月以内に〇kg減」
例えば、
❌ NG例:「とにかく痩せたい!」
🔴 OK例:「3か月で3kg減らし、体脂肪率を2%下げる」
こうすることで、具体的なゴールが見え、取り組みやすくなる。 - 小さな目標を積み重ねる(短期目標と長期目標を分ける)
「半年で10kg減らす」といった大きな目標を立てると、途中でモチベーションが下がりやすい。
短期目標を設定し、達成を積み重ねることで、継続しやすくなる。
▶ 短期目標と長期目標の設定
✔長期目標(最終的なゴール)
・「6か月で5kg減量し、ウエストを5cm細くする」
✔短期目標(1週間~1か月ごとの目標)
・「1か月で1kg減らす」
・「毎日10分ウォーキングする」
・「夕食の白米を100g減らす」
このように、短期目標を達成することで達成感を得られ、長続きしやすい。 - 目標を数値以外の視点でも考える
「体重を〇kg減らす」だけを目標にすると、体重が減らないときにやる気を失いがちである。
体重以外の目標も設定することで、「ダイエット」の成功体験を増やせる。
▶ 体重以外の目標例
✔見た目の変化
・「ウエストが5cm細くなる」「二の腕が引き締まる」
✔体調の変化
・「朝スッキリ起きられる」「疲れにくくなる」
✔習慣の変化
・「毎日30分歩く」「夜9時以降は食べない」
「体重が減らなくても、体脂肪率が下がった」「服のサイズがダウンした」といった変化を感じることで、「ダイエット」を続けるモチベーションにつながる。 - 目標を可視化し、定期的に振り返る
目標を立てても、途中で忘れてしまうと意味がない。
目標を紙に書いて見える場所に貼る、記録をつけるなどして、定期的に振り返ることが大切である。
▶ 目標を可視化する方法
✔「ダイエット」ノートをつける(毎日の体重・食事・運動を記録)
✔スマホのメモやカレンダーに目標を書き込む
✔Before-Afterの写真を撮る(週に1回、全身写真を撮影)
定期的に振り返ることで、進捗を把握し、モチベーションを維持しやすくなる。 - 目標達成のご褒美を設定する
「ダイエット」は長期戦であり、途中でモチベーションが下がることもある。
そのため、「目標を達成したら〇〇する」とご褒美を設定するのも効果的である。
▶ ご褒美の例
✔短期目標の達成ごとにプチご褒美
・「1kg減ったら新しい化粧品を買う」
✔長期目標の達成で大きなご褒美
・「5kg減ったら旅行に行く」
「目標を達成すれば楽しみがある」と思うことで、継続しやすくなる。
※「〇kg痩せる」といった曖昧な目標ではなく、具体的で達成可能な目標を立てることで、「ダイエット」を継続しやすくなる。
無理のない範囲で、楽しみながら「ダイエット」を続けることが成功のカギである。
② 食事制限が厳しすぎる
「ダイエット」を始めると、多くの人が「食べる量を減らさなければ」と考える。
しかし、極端な食事制限はストレスや栄養不足につながり、結果的にリバウンドを引き起こす原因となる。
無理なく続けられる、食事管理の方法は、以下の通り。
✅ 対策:食事管理の方法
- 極端な制限ではなく「バランス」を重視する
「糖質カット」「脂質制限」「○○だけダイエット」など、極端な食事制限は短期的に体重が減ることがあるが、続けるのは難しい。
▶ 食事制限ではなく、食事の“質”を改善する
✔糖質・脂質を適度に摂る(完全にカットせず、適量を意識)
✔たんぱく質をしっかり摂る(筋肉量を維持し、リバウンドを防ぐ)
✔野菜・食物繊維を多めにする(満腹感を得やすく、便秘予防にもなる)
✔「食べてはいけない」ではなく「何をどれだけ食べるか」を考える
例えば、
ご飯やパンを全く食べないのではなく、白米を玄米や雑穀米に変える、量を少し減らすなどの工夫で、無理なく糖質をコントロールできる。 - 「食べる楽しみ」を残す
食事が楽しめないと、「ダイエット」は長続きしない。好きなものを一切食べないのではなく、工夫して楽しむことが大切だ。
▶ 「我慢しすぎない」食事のコツ
✔「たまには好きなものを食べる日」を作る
・ 週に1回、好きなものを食べてもOK(ただし量は調整)
✔ダイエット向けの代替食品を活用する
・例えば、ポテトチップスの代わりにナッツや素焼き大豆、チョコの代わりにカカオ70%以上のチョコを選ぶ
✔食べ方を工夫する
・大好きなラーメンは「スープを残す」、揚げ物は「衣を薄めにする」など、少しの工夫でカロリーを抑えられる - 「食事量を減らす」より「食べる順番・タイミング」を意識する
「ダイエット」のために食べる量を極端に減らすと、空腹に耐えられずリバウンドしやすい。
食べ方を工夫することで、無理なく食事量を調整できる。
▶ 食べ方のポイント
✔「野菜→たんぱく質→炭水化物」の順に食べる
・血糖値の急上昇を防ぎ、脂肪がつきにくくなる
✔よく噛んで食べる(1口30回を目安に)
・満腹中枢が刺激され、少量でも満足しやすい
✔夜遅くの食事を避ける(寝る3時間前までに食べ終える)
・夜に食べると脂肪として蓄積しやすいため
✔間食は「質」と「量」を意識
・ナッツ、ヨーグルト、高カカオチョコ、チーズなど、腹持ちが良く栄養価の高いものを選ぶ - 「ダイエット食」ではなく「健康的な食生活」にシフトする
「ダイエット=食事制限」と考えるのではなく、健康的な食生活を意識することで、無理なく続けられる。
▶ 続けやすい食事のポイント
✔炭水化物は適量にし、たんぱく質をしっかり摂る(鶏むね肉、魚、豆類、卵)
✔野菜をたっぷり摂る(特に食物繊維の多い野菜を意識)
✔脂質は悪者にしない(良質な脂質:オリーブオイル、ナッツ、魚の脂)
✔水分をしっかり摂る(1日1.5L~2Lが目安) - 「完璧主義」をやめる
「絶対に食べない」「○○はNG」と厳しくしすぎると、続かないだけでなく、一度ルールを破ると諦めてしまう原因にもなる。
▶ 「80点でOK」の考え方を持つ
✔完璧にやろうとしない(多少のズレは気にしない)
✔「昨日食べすぎたから今日は調整しよう」と柔軟に対応する
✔ストレスを溜めず、楽しみながら続けることが大事
食事制限を厳しくしすぎると、ダイエットは続かない。
無理のない方法で、健康的な食生活を楽しみながら続けることが、成功のカギである。
※食事制限を厳しくしすぎると、「ダイエット」は続かない。
無理のない方法で、健康的な食生活を楽しみながら続けることが、成功のカギである。
③ 運動のハードルが高い
「ダイエット」の成功には運動が重要だと分かっていても、「ジムに通うのは面倒」「ハードなトレーニングは無理」「運動の習慣がないから続かない」と感じる人は多い。
運動のハードルが高いと感じると、「ダイエット」自体を諦めてしまうことにもつながる。
そこで、運動を気軽に取り入れ、継続できる方法は、以下の通り。
✅ 対策:継続する方法
- 「運動=ハードなもの」という固定観念を捨てる
運動と聞くと、「ランニング」「筋トレ」「ジム通い」などをイメージしがちだが、「ダイエット」に必要なのは日常的な活動量を増やすことである。
特別なトレーニングをしなくても、体を動かす機会を増やすことで、十分にカロリーを消費できる。
▶ こんな運動ならハードルが低い!
✔エレベーターを使わず階段を使う
✔買い物や通勤で意識的に歩く
✔家の掃除や片付けを運動と考える
✔ストレッチやラジオ体操を朝の習慣にする
✔テレビを見ながら足踏みやスクワットをする
これらを意識するだけでも、運動量は確実に増える。 - 「運動を頑張る」のではなく「日常に組み込む」
運動のために特別な時間を確保しようとすると、忙しさを理由に続かなくなる。
そこで、日常生活の中に運動を自然に取り入れるのがポイントだ。
▶ 生活の中に組み込む方法
✔「ながら運動」を取り入れる
・歯を磨きながらかかと上げ運動
・テレビを見ながらストレッチ
・信号待ちの間に軽くお腹を引き締める
✔通勤や買い物を運動の機会にする
・1駅手前で降りて歩く
・自転車を使う(速すぎないペースなら有酸素運動になる)
・買い物カゴを持ちながらスクワット(人にバレない程度に!)
✔立つ時間を増やす
・仕事中に座りっぱなしにならないよう、1時間に1回立ち上がる
・立ってできる作業(読書やスマホチェック)を座らずに行う - 短時間の運動から始める
「30分以上運動しないと効果がない」と思うと、気が重くなる。
しかし、短時間でも積み重ねれば十分に効果がある。
▶ 短時間でできる運動例
✔1回5分からOK!
・スクワット10回 × 3セット(約3分)
・軽いストレッチや体操(5分)
・寝る前に足上げ運動(3分)
✔「毎日30分」ではなく「1日トータル30分」を目指す
運動時間をまとめて取るのが難しい場合、5分×6回=30分という考え方にすると気が楽になる。 - 「楽しい」と思える運動を選ぶ
運動を「義務」と感じると、続けるのが苦痛になる。
自分が楽しめる運動を見つけることが大切だ。
▶ 楽しく運動する方法
✔音楽を聴きながらウォーキング
✔動画を観ながらエクササイズ(YouTubeのダンスやヨガ)
✔友達や家族と一緒に散歩
✔ゲーム感覚で運動(リングフィットアドベンチャー、ダンスゲームなど)
「運動をしなければ」と思うのではなく、「楽しいことをしながら体を動かす」と考えれば、気軽に続けやすい。 - 「運動しないとダメ」ではなく「少しでも動けばOK」と考える
「今日は運動できなかった」と自分を責めると、モチベーションが下がってしまう。
少しでも体を動かせばOKと考え、気楽に続けることが重要である。
▶ 「ゼロよりマシ」の精神を持つ
✔1分でも動けばOK
✔運動できなかった日も「今日は階段を使えた!」とポジティブに考える
✔完璧を目指さず、できる範囲で続ける
運動のハードルを下げることで、自然と「動くこと」が習慣化していく。
※「ダイエット」は「続けること」が何よりも大事である。
運動のハードルを下げ、自分に合った方法で無理なく続けることが、成功のカギとなる。
④ 結果がすぐに出ない
「ダイエット」が続かない理由の一つに、「結果がすぐに出ない」という問題がある。
多くの人は、短期間で目に見える変化を期待するが、実際には体重が減るまでに時間がかかる。
そのため、短期間で劇的に痩せることを期待しすぎると、停滞期に入ったときに「努力しても無駄だ」「努力しても意味がない」と感じ、挫折してしまうのだ。
ここでは、「ダイエット」の成果が出るまでの過程を理解し、モチベーションを維持するための具体的な対策は、以下の通り。
✅ 対策:モチベーションを維持する方法
- ダイエットの成果が出るまでの過程を知る
まず、「ダイエット」の進み方を理解することが重要である。
一般的に、体重が減るまでには以下のような段階を経る。
▶1~2週間:体重があまり減らない時期(停滞期)
✔食事管理や運動を始めても、最初の数週間は大きな変化が出にくい。
✔体が変化に適応するため、脂肪がすぐに燃焼し始めるわけではない。
✔しかし、代謝が少しずつ上がり、体の内側では変化が始まっている。
▶3~4週間:少しずつ変化が現れる時期
✔体脂肪が燃え始め、体重がゆるやかに減少する。
✔見た目の変化よりも、体調の改善(疲れにくくなる、体が軽く感じる)を実感しやすい。
✔ウエストや顔周りが少しスッキリしてくる。
▶1~3か月:目に見える変化が出る時期
✔ここまで続けると、体重・体脂肪ともに明確な変化が出る。
✔服のサイズが変わったり、鏡で見ても違いが分かるようになる。
✔継続することで、リバウンドしにくい体質が作られる。 - すぐに結果が出なくても挫折しないための対策
▶短期間の結果ではなく、長期的な視点を持つ
「ダイエット」は1~2週間で劇的に変わるものではない。
「3か月後」「半年後」など、長期的な目標を設定することで、モチベーションを維持しやすくなる。
▶体重だけにこだわらず、他の変化を記録する
体重の変化が少ないと、「ダイエット」が成功していないように感じるが、実際には体脂肪が減っていたり、筋肉がついて代謝が上がっている可能性がある。
✔体重以外の変化をチェックする
・ウエストや太もものサイズを測る
・鏡で自分の体の変化を確認する(写真を撮るのも◎)
・体が軽くなったり、疲れにくくなったりするかを意識する
・睡眠の質や肌の調子の変化を記録する
▶「見た目の変化」が分かるように、定期的に写真を撮る
毎日鏡を見ると変化に気づきにくいが、1週間ごとに写真を撮ると、少しずつスリムになっていることが分かる。
▶短期的な目標を作り、小さな成功を積み重ねる
「1か月で-5kg」といった大きな目標だけでなく、小さな達成目標を作ると続けやすい。
✔例:短期目標の設定方法
・1週間で間食を減らす
・1日30分歩くことを1週間続ける
・毎日水を1.5リットル飲む
・夜9時以降に食べない習慣を作る
▶「できたこと」に目を向け、自己肯定感を高める
「まだ体重が減らない」とネガティブに考えるのではなく、「今日はお菓子を我慢できた」「運動が続いている」とポジティブに考えることが重要である。
▶周囲の影響を受けにくくする
「すぐに痩せないなら意味がない」と思うのは、周囲の期待や比較による影響が大きい。
自分のペースでコツコツ続ける意識を持とう。 - ダイエットを継続するための工夫
▶無理な「ダイエット」ではなく、「続けられる習慣」を作る
極端な食事制限や過度な運動は、短期間で痩せてもリバウンドしやすい。
続けられる範囲で食事や運動を調整することが大切だ。
✔続けやすい「ダイエット」方法
・「糖質を減らす」ではなく、「糖質を選ぶ」(白米を玄米にする、パンを全粒粉にするなど)
・「運動しなきゃ」ではなく、「好きな動きをする」(ダンス、ストレッチ、ラジオ体操でもOK)
・「お菓子をゼロにする」ではなく、「量を決めて食べる」(チョコ1個ならOK、週に1回ならOKなど)
▶ダイエット仲間を作る
一人だと挫折しやすいが、同じ目標を持つ仲間がいるとモチベーションが上がる。
家族や友人と一緒に取り組むのも良い方法だ。
▶ご褒美を設定する
「1週間続けられたら好きなドラマを観る」「1か月続いたらマッサージに行く」など、小さなご褒美を設定すると楽しみながら継続できる。
※「ダイエット」は、長期的な視点を持ち、焦らず続けることが成功のカギである。
すぐに結果が出なくても、確実に体は変わっていることを信じ、楽しく続けていこう。
⑤ ストレスや生活習慣の影響
「ダイエット」が続かない理由の一つに、「ストレス」や「生活習慣」の影響がある。
仕事や人間関係のストレス、睡眠不足、不規則な食生活などは、「ダイエット」の成功を妨げる大きな要因となる。
ここでは、ストレスや生活習慣が「ダイエット」に与える影響と、それを克服するための具体的な対策は、以下の通り。
✅ 対策:ストレスや生活習慣の影響とその対策
- ストレスがダイエットに与える影響
ストレスが溜まると、以下のような問題が起こりやすい。
▶暴飲暴食を引き起こす
ストレスが溜まると、脳が「快楽を求める行動」を優先し、高カロリーな食べ物を欲しがる。
特に、甘いものや脂っこいものはストレス解消の手段になりやすい。
▶ホルモンバランスが乱れ、脂肪がつきやすくなる
ストレスを感じると、「コルチゾール」というホルモンが分泌される。
このホルモンは、体に脂肪を蓄えやすくし、特にお腹周りの脂肪が増えやすくなる。
▶モチベーションの低下
ストレスが続くと、「ダイエット」のやる気がなくなり、途中で諦めてしまうことが多い。
▶睡眠不足につながる
ストレスによる不眠は、食欲を増進させるホルモン(グレリン)を増やし、逆に食欲を抑えるホルモン(レプチン)を減らす。
その結果、過食しやすくなる。 - ストレスをコントロールする対策
▶ストレス解消法を取り入れる
「ダイエット」中は「食べること」以外のストレス解消法を持つことが大切である。
おすすめのストレス解消法
✔運動をする(ウォーキングやヨガはストレス軽減に効果的)
✔趣味を楽しむ(読書、音楽、ゲーム、映画鑑賞など)
✔深呼吸や瞑想をする(リラックス効果がある)
✔温かいお風呂に入る(副交感神経を刺激し、ストレスを和らげる)
✔睡眠の質を上げる(寝る前のスマホを控え、快適な寝室環境を作る)
▶「ストレス食い」の代替行動を用意する
「ストレスを感じたら、○○をする」と事前に決めておくと、暴飲暴食を防ぎやすい。
代替行動の例
✔甘いものが欲しくなったら、ハーブティーを飲む
✔無性に食べたくなったら、軽くストレッチや散歩をする
✔口寂しいときは、ナッツやヨーグルトを少量食べる - 生活習慣の改善がダイエット成功のカギ
▶生活リズムを整える
不規則な生活は、ホルモンバランスを乱し、食欲をコントロールしにくくなる。
規則正しい生活のポイント
✔毎日同じ時間に起きる・寝る
✔朝食をしっかり食べる(体内時計をリセットし、食欲を安定させる)
✔夜遅くの食事を控える(寝る3時間前には食事を終える)
▶睡眠をしっかりとる
睡眠不足は「ダイエット」の大敵である。
良質な睡眠をとるための工夫:
✔寝る1時間前にはスマホやPCの使用を控える
✔カフェインを夕方以降に摂らない
✔寝る前に軽いストレッチや深呼吸をする
▶運動習慣を取り入れる
運動にはストレス解消と「ダイエット」の両方の効果がある。
おすすめの運動
✔ウォーキング(1日30分でもOK)
✔ストレッチやヨガ(リラックス効果がある)
✔軽い筋トレ(筋肉量を増やし、代謝を上げる)
▶食生活を見直す
乱れた食生活は、「ダイエット」の妨げになる。
健康的な食習慣のポイント
✔バランスの取れた食事を心がける(炭水化物・タンパク質・脂質のバランスを意識)
✔よく噛んで食べる(満腹感を得やすく、食べ過ぎを防ぐ)
✔食事の時間を決める(間食を減らすために、規則的に食べる) - 「完璧主義」をやめる
「ダイエット」中は「絶対に甘いものを食べない」「運動をサボらない」と完璧を求めがちだ。
しかし、完璧を求めすぎると、少しの失敗でモチベーションが下がり、挫折しやすくなる。
▶失敗してもOK!の考え方
✔「今日は食べすぎたから、明日は調整しよう」
✔「1回運動をサボっても、また明日からやればいい」
✔「長期的に続けることが大切だから、焦らなくてもいい」
「ダイエット」は短期間で終わるものではなく、一生続く「生活習慣の改善」である。
完璧を求めず、80%くらいの達成率でOKと考えることで、無理なく続けやすくなる。
※「ダイエット」は「短期間で頑張るもの」ではなく、「一生続ける健康的な習慣」である。
ストレスや生活習慣の影響をコントロールしながら、無理なく続けることが成功への近道だ。
⑥ ダイエットの目的が明確でない
「ダイエット」に挑戦する人の中には、「何となく痩せたい」「健康に良さそうだから」といった曖昧な理由で始める人が多い。
しかし、目的が明確でないと、途中でモチベーションが下がり、失敗する可能性が高くなる。
ここでは、目的を明確にし、「ダイエット」を成功させるための具体的な対策は、以下の通り。
✅ 対策:成功させるための方法
- 具体的な目標を設定する
「痩せたい」というだけでは漠然としており、達成基準がわからない。
そこで、目標を具体的に設定することが重要である。
▶ 目標設定のポイント
✔数値を明確にする(例:「3ヶ月で5kg減」「体脂肪率を3%減らす」)
✔健康を意識した目標を立てる(例:「血圧を正常値に戻す」「膝への負担を減らす」)
✔見た目や衣類を基準にする(例:「お気に入りのスーツを着られるようにする」)
✔運動能力向上を目指す(例:「1日1万歩歩けるようにする」「腕立て伏せを10回できるようにする」)
目標が具体的であればあるほど、進捗がわかりやすく、達成意欲が高まる。 - ダイエットの「本当の目的」を考える
「なぜダイエットをするのか?」を深掘りすることで、より強い動機づけができる。
✔見た目を良くしたい → なぜ?👉 「若々しく見られたい」「自信を持ちたい」
✔健康のため → どんな健康問題を改善したい?👉 「高血圧を改善したい」「膝の負担を減らしたい」
✔運動パフォーマンスを上げたい → なぜ?👉 「子どもや孫と一緒に元気に遊びたい」「旅行でたくさん歩きたい」
こうした「本当の目的」を意識すると、挫折しそうになったときに踏ん張れる。 - 目標を見える化する
目標を設定したら、それを見える形にすることが大切である。
▶ 具体的な方法
✔紙に書いて毎日目につく場所に貼る(例:「3ヶ月後にこのスーツを着る!」)
✔スマホの待ち受けに目標を表示する
✔体重や体脂肪率をグラフ化する
✔日記やSNSで記録する(「1週間で1kg減った!」など)
目標を視覚化することで、日々のモチベーションを維持しやすくなる。 - 小さな成功を積み重ねる
いきなり大きな変化を求めると、挫折しやすい。そこで、短期間で達成できる小さな目標を設定し、成功体験を積み重ねることが大切だ。
▶ 短期目標の例
✔1週間で運動の習慣をつける(毎日5分ストレッチをする)
✔1週間で間食を減らす(お菓子をナッツやヨーグルトに置き換える)
✔毎日体重を測る習慣をつける
これらを達成することで、「できた!」という実感が湧き、モチベーションが継続しやすくなる。 - 目的に合わせたダイエット方法を選ぶ
目的が明確でないと、「ダイエット」方法も適当に選びがちになる。目的に合った方法を選ぶことで、効果的に取り組める。
▶ 目的別の「ダイエット」方法
✔見た目を引き締めたい → 筋トレ+食事管理
✔体重を落としたい → 有酸素運動+カロリーコントロール
✔健康を改善したい → 食生活改善+適度な運動
✔体力をつけたい → ストレッチ+筋トレ+ウォーキング
目的に合った方法で取り組めば、無駄な努力をせずに済み、継続しやすい。 - ダイエットを「楽しむ」工夫をする
目的を明確にしても、「ダイエット=辛い」と感じると続かない。そこで、楽しみながら続ける工夫が必要である。
▶ 具体的な工夫
✔好きな音楽や動画を見ながら運動する
✔料理を楽しみながら低カロリーメニューを作る
✔「ダイエット」仲間と情報交換する
✔ご褒美を設定する(例:1ヶ月続いたら新しいウェアを買う)
楽しく続けられる環境を作ることで、モチベーションが維持しやすくなる。
※「なんとなく痩せたい」ではなく、「このために痩せる!」という明確な理由を持つことで、「ダイエット」の成功率は格段に上がる。
⑦ 周囲の影響を受けやすい
「ダイエット」中は、家族・友人・職場の環境に左右されやすい。
しかし、完全に孤立するのではなく、「工夫して付き合う」ことが大切だ。
「ダイエット」の失敗原因のひとつに「周囲の影響を受けやすい」という問題がある。
家族や友人、職場の環境が「ダイエット」に対して協力的でない場合、食事の誘惑やネガティブな言葉によってモチベーションが低下し、途中で挫折してしまうことが多い。
家族や友人との食事の機会が多いと、つい誘惑に負けてしまう。
また、「そんなに頑張らなくてもいいのでは?」といった周囲の言葉に影響されることもある。
その具体的な対策は、以下の通り。
✅ 対策
- 家族との食事対策
▶ 家族の食事と自分の食事を完全に分けない
家族と一緒に食事をする場合、自分だけ極端に違う食事をしているとストレスが溜まり、長続きしない。
家族のメニューの中で、カロリーを抑えられるものを選んだり、調理法を工夫することで、無理なく「ダイエット」ができる。
具体例
✔揚げ物を焼き料理や蒸し料理に変える
✔白米を雑穀米や玄米に置き換える
✔取り分ける量を少し減らし、野菜を多めに食べる
▶ 家族に「ダイエット」の目的を理解してもらう
「健康のためにダイエットをしている」ということを家族に伝えることで、協力を得やすくなる。
「一緒に健康的な食事を楽しもう」とポジティブに伝えると、家族も巻き込みやすい。 - 友人との付き合い方
▶ 外食時のメニュー選びを工夫する
友人との食事を完全に断るのではなく、メニュー選びを工夫することで無理なく楽しめる。
具体例
✔居酒屋では揚げ物ではなく、焼き魚や刺身、豆腐料理を選ぶ
✔定食なら、ご飯を少なめにするか、サラダを追加する
✔ファストフードなら、ポテトをサラダに変更する
▶ 友人に「ダイエット」中であることを伝える
「最近、健康のために食事に気をつけている」と軽く伝えておくと、周囲も無理に高カロリーなものを勧めなくなる。
「でも、たまには好きなものを食べるよ!」と柔軟な姿勢を見せることで、プレッシャーを感じることなく付き合いを続けられる。 - 職場環境の対策
▶ 差し入れやお菓子の誘惑を避ける
職場では差し入れのお菓子や付き合いでのランチが多く、「ダイエット」の大きな障害となることがある。
具体例
✔「今は甘いもの控えてるから、また今度ね」とやんわり断る
✔どうしても断れない場合は、一口だけ食べて「美味しい!」と言って満足する
✔自分用に低カロリーの間食(ナッツ、ヨーグルトなど)を持参し、空腹を防ぐ
▶ 昼食の選択肢を決めておく
職場のランチでは、高カロリーなものを選びがち。
あらかじめ「ランチは和定食」「丼ものならご飯は半分にする」など、自分の中でルールを決めておくと、無駄な誘惑を防げる。 - 周囲の「ネガティブな言葉」への対処法
「ダイエット」をしていると、以下のような言葉をかけられることがある。
✔「そんなに頑張らなくてもいいのでは?」
✔「ちょっとくらい食べても大丈夫だよ!」
✔「どうせまたリバウンドするよ」
こうした言葉に影響されないためには、「相手の意見は気にせず、自分の目標に集中する」ことが大切だ。
▶「やんわり受け流す」
「そうなんだよね。でも今ちょっと健康を意識してるんだ」など、軽く流せば、相手も無理に干渉してこなくなる。
▶「ポジティブな言い方で伝える」
「ダイエットしてる」というより、「体調を整えたい」と言う方が、周囲も受け入れやすい。
健康管理の一環として伝えると、応援してくれる人が増えることもある。 - ダイエット仲間を作る
▶ 一緒に頑張る仲間を見つける
周囲が非協力的でも、一緒に「ダイエット」を頑張る仲間がいればモチベーションを維持しやすい。
具体例
✔ウォーキングやジムに一緒に行く友人を作る
✔SNSやダイエットアプリで経過を記録し、他の人と励まし合う
✔家族や同僚の中で「健康を意識している人」と情報交換する
▶ 「応援してくれる人」を大切にする
すべての人がダイエットに協力的とは限らないが、応援してくれる人を見つけて、その人とコミュニケーションをとることで、周囲の影響をポジティブに変えることができる。
※周囲に振り回されず、自分のペースでダイエットを続けることが成功へのカギとなる。
2.人の心理(心構え)
①「完璧主義を捨てる」
1回食べ過ぎてもリカバリーすればOK!
「0か100か」ではなく、「70点を続ける」意識を持つ。
②「短期ではなく長期目線を持つ」
1週間で劇的に変わらなくても、3ヶ月後には確実に変わる。
「1日単位」ではなく「1ヶ月単位」で成果を見る。
③「楽しみながら継続する」
好きな食べ物を完全に禁止せず、バランスを考えて取り入れる。
運動は「嫌々やる」ではなく、楽しめるものを選ぶ(ダンス、ウォーキング、ヨガなど)。
④「成功体験を積み重ねる」
体重以外にも「ウエストが細くなった」「階段が楽になった」など、小さな変化を喜ぶ。
SNSや日記で変化を記録し、自分を褒める。
ダイエットを成功させ、リバウンドなく習慣化する方法
成功するためには、以下のポイントを意識することが重要である。
- 目標を「長期的」に設定する
「1ヶ月で5kg痩せる」よりも、「半年かけて5kg減」「1年後に健康診断の数値を改善する」といった長期的な目標を立てるほうが、無理なく続けやすい。 - 完璧を求めず「7割の成功」を目指す
「ダイエット」中でも好きなものを楽しむことが大切だ。
例えば「週に1回は好きなものを食べる」「毎日30分歩くのが無理なら、まずは10分でもOK」といった柔軟な考えを持つことが継続のカギとなる。 - 体重だけでなく「体型の変化」を意識する
体重が変わらなくても、ウエストのサイズや姿勢、肌の調子などが良くなっているかもしれない。
数字だけでなく、体の変化を楽しむことがモチベーション維持につながる。 - 「習慣化」することを意識する
「ダイエット」は特別なことではなく、「新しい生活習慣」として定着させることが大切だ。
朝のストレッチ、食事のバランス、適度な運動を「無理なくできる範囲」で取り入れよう。 - 食べ物のカロリーを知る
1食あたりのエネルギー摂取量を把握することで、適切な1日分の食事量をコントロールできる様になる。
果物やお菓子などのカロリーを知ることで、食べ過ぎないようになる。 - 日常生活における消費カロリーを知る
家事(掃除、洗濯、片付けなど)や立ち仕事の消費カロリーを把握する。
10分あたりの消費カロリーを意識することで、日常生活の中で自然にエネルギーを消費できる。
意外に、家事や立ち仕事が、カロリーを消費することに驚くだろう。
※参考データ
摂取カロリー早見表
毎日の食事の摂取エネルギー量を知り、生活習慣を見直してみましょう。
※記載のカロリーは1人分です。摂取カロリーカテゴリー
基本メニュー和食
洋食
中華
デザート/飲み物
引用元:タニタ 摂取カロリー早見表
消費カロリー早見表
ご自身の消費エネルギー量を知り、生活習慣を見直してみましょう。 ※メッツとは、身体活動の強さ(強度)を表す単位です。座って安静にしている状態を1メッツとし、身体活動の強さがその何倍に相当するかを表します。一般的に普通歩行(平地,67m/分程度)はおよそ3メッツになります。つまり、座って安静にしている状態の約3倍の活動の強さということです。 ※記載値は一般的な値であり、メッツ(身体活動の強さ)や消費エネルギー量は個人差がありますので、参考としてご覧ください。
消費カロリーカテゴリー
家事
育児
日常生活
趣味
仕事中
※一部抜粋
- 出典: 戸山芳昭ら,「健康づくりのための身体活動基準 2013」,厚生労働省,2013年 をもとに作成
- 記載値は一般的な値であり、メッツ(身体活動)や消費エネルギー量は個人差がありますので参考としてご覧ください。
引用元:タニタ 消費カロリー早見表
- 本コラムに記載されている情報は掲載日時点のものです。内容は予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
まとめ
「ダイエット」成功の鍵は、完璧を求めすぎず、無理のない方法を選ぶこと、そして、習慣化と継続にある。
体の変化は、段階的に現れ、初期には、体重の減少やむくみの改善が見られ、停滞期を経て、脂肪燃焼が進み、最終的には、健康的な体型を維持できるようになる。
しかし、その過程で、多くの人が挫折するのは、「ダイエット」が単なる行動ではなく、感情と深く結びついているからである。
人は「痩せたい」と意識することで期待を膨らませ、結果が出ないと、焦りやストレスを感じる。
この心理的な揺れが、「ダイエット」の継続を困難にする要因の一つである。
下記は、ダイエットの各期間における、「体の変化・心理状態・対策・覚えておくこと」を簡単に一覧表にしたものだ。
「体と心」に焦点をあてたもので、参考になったら幸いだ。
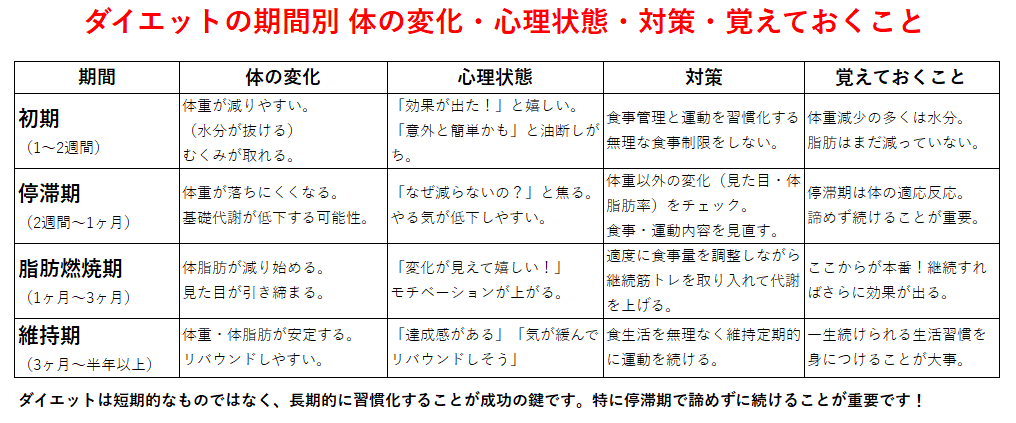
そのため、「ダイエット」を成功させるには、目標を明確にし、小さな成功を積み重ねながら、生活の一部として自然に取り入れることが重要なのだ。
「ダイエット」は、一種の「精神修行」のような側面も持っているようだ。
「痩せなければならない」と強く意識しすぎると、逆にプレッシャーとなり、途中で投げ出したくなる。
一方で、余計な雑念を捨て、「決めたことを淡々とこなす」という姿勢を持てば、苦痛を感じることなく習慣として根付くだろう。
食事管理や運動を「やらなければならないもの」ではなく、「当たり前の行動」として受け入れることが、長期的な成功につながるに違いない。
「ダイエット」は、一時的な努力ではなく、「生活習慣を改善すること」が目的であり、「一生続けるべき健康的なライフスタイル」なのだ。
結果に一喜一憂せず、ただ日々の積み重ねを続けることこそが、理想の体型と健康を手に入れる最善の「道」である。
「ダイエット」には「ゴールは無い」のだから、決して「近道は無い」という事を意識するべきだ。
「ダイエット」は、体重の数字だけでなく、体型や健康状態の変化を楽しみながら続けることが、リバウンドを防ぎ、長く健康を維持する秘訣である。
「ダイエット=苦しいもの」ではなく、「健康な生活を手に入れる過程」と考え、「生涯を通じて」楽しみながら継続していこう。