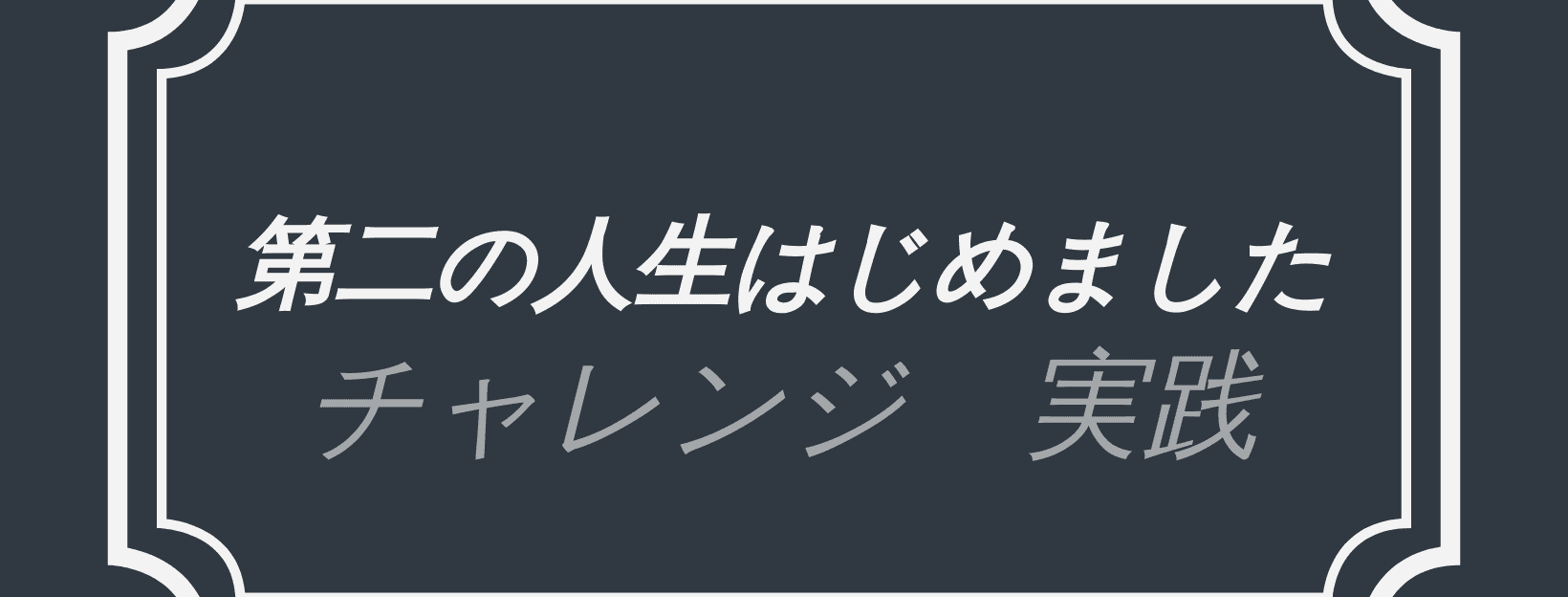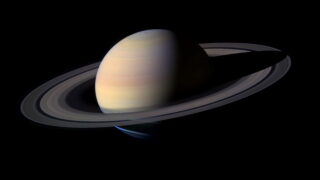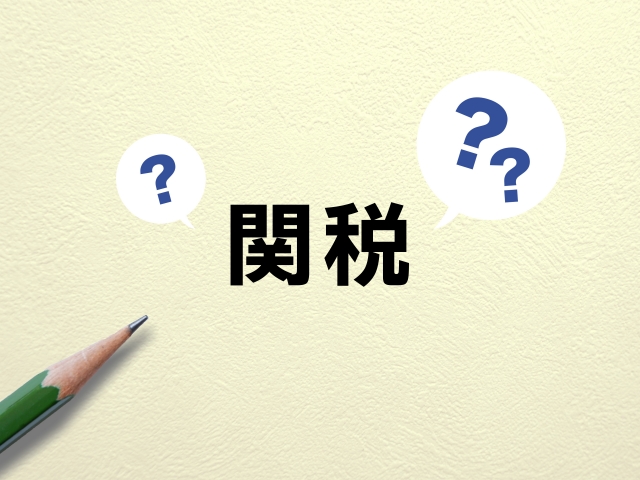2025年1月20日に返り咲きを果たした、ドナルド・トランプ大統領は、第1政権時代(在任:2017年1月20日 ~ 2021年1月20日)に、「関税」という言葉を、交渉の武器として多用し、自らを「タリフマン:Tariff Man(関税男)」と称した。
2018年12月、米中貿易戦争の最中に、当時のトランプ大統領は、Twitter(現X)で「私は関税男だ(I am a Tariff Man)」と投稿し、関税を経済政策の中心に据える姿勢を強調した。
さらに2019年5月には、「最も美しい言葉は関税だ(The greatest word is Tariff)」と発言し、「関税」こそが、国家の繁栄を支える鍵であると主張していた。
そして、2025年1月20日に、第47代アメリカ合衆国大統領に就任したトランプ大統領は、「関税」を単なる経済政策にとどめず、「外交交渉の切り札」として活用しようとしている。
その背景には、アメリカ第一主義(America First)の理念があり、貿易赤字の是正や国内産業の保護を目的とした、積極的な「関税」戦略が展開されたのである。
ここでは、「関税」を巡るトランプ大統領の発言と、その意図を掘り下げ、今後、トランプ大統領は、「関税」をどのように用いていくのか、想像して見ていきたい。
「関税:タリフ(tariff)」とは何か?
「関税:タリフ(tariff)」とは、外国から輸入される商品に対して政府がかける「税金」のことである。
「税金」を表す言葉には、「タックス(tax)」があるが、我々が良く耳にするのがこれである。
一方、トランプ大統領の使った言葉は、「タリフ(tariff)」の方だ。
この違いを簡単に言うと、「タックス(tax)」は税金全般、「タリフ(tariff)」は輸入品・輸出品にかかる「関税」、を表している。
トランプ大統領が言っているのは、外国製品にかける「関税」(import tariff)は、「タリフ(tariff)」であり、輸入品に対する税金という事となる。
たとえば、日本にアメリカ産の牛肉が輸入される際、日本政府が一定の税率で「関税」を課すことで、その牛肉の価格は上がる。
「関税」は、国内産業を守るためや、政府の収入を確保するために設定されるものであり、国ごとに異なるルールがある。
「関税」は、国内産業を守るために必要な一方で、消費者や企業にとっては価格の上昇というデメリットがある。
また、「関税」は、貿易交渉の道具としても使われ、各国の経済に大きな影響を与える。
トランプ大統領が「関税こそ最強の武器」と考えたのも、この影響力の大きさを理解していたからにほかならない。
「関税:タリフ(tariff)」の基本と目的
「関税」の主な目的は、①国内産業の保護、②政府の税収確保、③貿易政策の調整の3つに分けられる。
- 国内産業の保護
海外から安い商品が大量に流入すると、国内の企業が価格競争で負けてしまう可能性がある。
たとえば、日本で農家が作る米が1kgあたり500円なのに、外国から安い米が1kg300円で輸入されれば、日本の農家は大きな打撃を受ける。
そこで政府は輸入米に「関税」をかけ、最終的な価格を国内産の米と同じくらいにすることで、日本の農家を守るのである。 - 政府の税収確保
「関税」は、政府にとって重要な収入源の一つである。
輸入品に「関税」をかけることで、国内に入ってくる商品から税金を徴収できる。
特に、新興国では、消費税や所得税よりも、「関税」が大きな税収を占める国もある。 - 貿易政策の調整
「関税」は、他国との交渉材料にもなる。
たとえば、ある国が日本の自動車に高い「関税」をかけた場合、日本もその国の製品に「関税」をかけることで、条件を対等にしようとする。
このように、「関税」は、貿易交渉において重要な役割を果たす。
「関税:タリフ(tariff)」が貿易に与える影響
「関税」をかけることで、商品価格が上がり、消費者や企業にさまざまな影響を及ぼす。
- 価格の上昇
「関税」がかかると、輸入品の価格は高くなる。
たとえば、海外から1台100万円の車を輸入する際に20%の関税がかかると、その車の価格は120万円になる。
この結果、消費者はより高い価格で商品を購入しなければならなくなる。 - 消費者への影響
「関税」によって輸入品の価格が上がると、消費者はより高い価格で商品を買わなければならなくなる。
たとえば、海外の安い果物や食品に高い「関税」がかけられると、スーパーでの価格も上がり、家計の負担が増える。 - 企業への影響
「関税」は、企業にも影響を与える。
たとえば、日本の自動車メーカーがアメリカに車を輸出する際、アメリカが「関税」をかければ、日本の車は現地で高くなり、販売が落ち込む可能性がある。
また、「関税」によって原材料のコストが上がれば、日本の企業が作る商品の価格も上がり、競争力が低下することになる。
「関税:タリフ(tariff)」は誰が負担するのか?
「関税」は、輸入業者が負担する。
「関税」は、輸入品に課される税金で、輸入取引により輸入される貨物を輸入する者が、納税義務者となる。
「関税」が輸入業者に課される場合でも、その影響は輸入業者だけでなく、国内産業全体に波及する。
業者が事業を維持するために価格を抑えたとしても、以下のような影響が考えられる。
- 輸入業者の負担増加と経営圧迫
輸入品に「関税」がかかると、業者は本来の仕入れ価格に加えて追加のコストを負担する必要がある。
しかし、競争のために価格を据え置くと、利益が減少し、最悪の場合は経営が難しくなる可能性がある。 - 国内産業への影響
「関税」がかかることで、輸入品の価格が上昇すれば、相対的に国内製品が有利になる。
これは国内産業の保護につながる一方で、輸入業者が価格を抑えた場合、次のような影響が出る可能性がある。
価格競争の激化:
輸入業者が価格を抑え続けると、国内の同業者も価格を下げざるを得ず、利益率が低下する。
品質競争へのシフト:
価格を下げられない国内メーカーは、品質やブランド力を強化して競争しようとするが、それには追加のコストが必要。
原材料コストの影響:
「関税」が原材料や部品にかかる場合、国内メーカーも生産コスト増加に直面し、利益圧迫のリスクがある。 - 消費者への影響
輸入業者が価格を抑えられれば、消費者の負担は軽減される。
しかし、それが長期的に続くと輸入業者が撤退し、選択肢が減少する可能性がある。
また、国内産業が価格競争で疲弊すれば、結果的に市場の健全性が損なわれる。 - 長期的な影響
短期的には、輸入業者が「関税」の負担を吸収することで、国内産業への影響が抑えられることもある。
しかし、長期的には以下のような問題が生じる可能性がある。
輸入業者の撤退:
利益が確保できなければ、輸入業者が事業を縮小・撤退し、結果的に国内市場の競争が低下。
国内企業の過剰依存:
「関税」によって守られた国内企業が、競争力強化を怠ると、「関税」が撤廃された際に市場で生き残れなくなる。
第1次トランプ政権の「関税政策」
トランプ大統領は、第1次政権時代において、「関税」を単なる経済政策ではなく、外交交渉の強力な武器として活用した。
「関税」を引き上げることで他国に圧力をかけ、アメリカに有利な条件を引き出すことを狙ったのである。
この手法は、特に貿易交渉の場面で顕著に見られ、実際にいくつかの国との交渉で成果を上げた。
新たなFTA締結で在米日系企業にポジティブな効果も
関税政策による負の影響への注目が高まるが、トランプ次期政権下で取られ得る通商政策のうち、ビジネスに好ましい効果が期待されるものもある。その1つが自由貿易協定(FTA)交渉の再開だ。共和党の政策綱領では、既述の関税政策などのほか、「失敗した協定を再交渉する」とも記されている。トランプ氏は、自由貿易体制をしばしば批判しているが、米国の輸出を拡大するFTAには必ずしも反対しているわけではない。自身より前の政権が交渉して成立させたFTAは「米国にとって悪い」ものであり、それを再交渉することによって、「米国にとって良い」協定に作り替えるとの立場だ。例えば、2018~2019年に改定した米韓FTAの再交渉では、米国がトラックの輸入に課す25%の関税撤廃時期を2021年から2041年に延期したほか、北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉では、米国内で一層の生産を促すため、完成車の原産地規則を厳格化した米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)を締結した(表3参照)。
引用元:日本貿易振興機構(ジェトロ)外交手段としての関税政策、トランプ関税の日本への影響
1.米中貿易戦争(対中国)
トランプ政権が最も積極的に「関税」を用いたのが、中国との貿易戦争である。
2018年、トランプ大統領は「中国が不公正な貿易慣行を行っている」として、中国からの輸入品に対して大規模な「関税」措置を導入した。
具体的な関税措置
- 2018年7月:340億ドル相当の中国製品に25%の「関税」
- 2018年9月:さらに2,000億ドル分に10%の「関税」(のちに25%へ引き上げ)
- 2019年12月:スマートフォンやノートパソコンを含む1,600億ドル分に追加「関税」
狙いと影響
トランプ政権は、この「関税」措置によって中国に圧力をかけ、アメリカの貿易赤字を削減し、中国の知的財産侵害や技術移転の強要を是正しようとした。
その結果、2020年1月に「第一段階の貿易合意」が成立し、中国はアメリカ産農産物や工業製品の輸入を増やすことを約束した。
しかし、米中関係はさらに悪化し、貿易摩擦が長期化する要因ともなった。
2.自動車関税をちらつかせた対日・対EU交渉(対日本・EU)
トランプ大統領は、日本やEUに対しても、自動車「関税」を交渉のカードとして利用した。
日本への圧力
2018年、トランプは、「日本がアメリカの自動車産業を脅かしている」と主張し、日本からの輸入車に25%の「関税」をかける可能性を示唆した。
これにより、日本政府は、アメリカとの貿易交渉に応じ、2019年の日米貿易協定が締結された。
この協定では、日本が、アメリカ産牛肉や豚肉の「関税」を段階的に引き下げる一方、アメリカは、自動車「関税」を当面据え置く形となった。
EUとの交渉
同様に、トランプはEUに対しても「ドイツ車などの輸入に関税をかける」と圧力をかけた。
これを受けてEUは、アメリカ産の大豆や天然ガスの輸入を拡大する方針を示し、一定の妥協が成立した。
3.メキシコへの関税脅迫(対メキシコ)
トランプ大統領は、貿易交渉だけでなく、移民政策にも「関税」を利用した。
2019年、アメリカへの不法移民問題をめぐり、トランプは「メキシコが不法移民の流入を阻止しなければ、すべてのメキシコ製品に対し5%の関税を課す」と警告した。
結果
メキシコ政府はこの圧力を受け、移民対策を強化することを決定。
アメリカとの合意により、メキシコ国内での移民取り締まりを強化し、国境管理の強化策を導入した。
最終的に、トランプ大統領は、「関税」の発動を見送ったが、「関税」を外交ツールとして活用する手法が成功した例となった。
第2次トランプ政権の「関税外交」とその狙い
2025年1月20日、トランプ大統領が再び政権を握る事となった。
今後のトランプ大統領の「関税外交」は、さらに強化される可能性が高いと考えられている。
トランプ大統領は、「関税は交渉の武器であり、アメリカの利益を最大化するための手段である」という考えを持ち続けており、実際の貿易交渉や国際関係において、「関税」を大胆に活用すると予測される。
ここでは、2025年以降に起こりうる、具体的な「関税政策」と、その影響について想像してみよう。
1.米中貿易戦争の再燃:より強硬な対中政策
トランプ大統領は、2020年の大統領選挙キャンペーンから一貫して「中国はアメリカ経済を不当に搾取している」と主張しており、2025年以降も対中「関税」を強化する可能性が高い。
具体的な措置の予測
- 対中関税の再強化
- 2018〜2019年に課された「関税」(25%)をさらに引き上げる可能性
- 半導体・EV(電気自動車)・AI技術関連製品への新たな「関税」導入
- アメリカ企業の中国撤退を促すための追加「関税」
狙いと影響
トランプ大統領は、これらの「関税」を通じて、中国との経済的なデカップリング(分離)を加速させ、アメリカ国内での製造業復活を促す意図がある。
しかし、中国も報復「関税」やレアアースの輸出制限を行う可能性があり、米中経済関係の緊張はさらに高まると予測される。
2.日本・EUへの自動車関税の再検討
2018〜2019年、トランプ大統領は、日本とEUに対して「アメリカに輸出される自動車に最大25%の「関税」をかける」と警告した。
2025年の政権復帰後、この政策が再び持ち上がる可能性がある。
具体的な措置の予測
- 日本・EUからの自動車輸入に10〜25%の「関税」を課す可能性
- 交渉材料として「関税」をちらつかせ、日本・EUにアメリカ製自動車の輸入拡大を要求
狙いと影響
日本やドイツの自動車メーカーはアメリカ市場への依存度が高く、「関税」が導入されれば価格競争力が低下する。
一方、日本やEU側は報復措置としてアメリカ製品への「関税」を引き上げる可能性があり、日米・米欧関係が緊張する恐れがある。
3.メキシコ・カナダへの「USMCA再交渉」圧力
トランプ大統領は、2018年、北米自由貿易協定(NAFTA)を廃止し、新たに「USMCA(米・メキシコ・カナダ協定)」を締結した。
しかし、2025年以降、トランプ大統領が「アメリカにとって不利な内容がある」と主張し、USMCAの再交渉を要求する可能性がある。
具体的な関税措置の予測
- メキシコ製品(自動車、電化製品)への新たな「関税」導入
- カナダの木材・乳製品への「関税」引き上げ
- メキシコに対する移民対策の圧力として「関税」を利用
狙いと影響
トランプ大統領は、「アメリカ国内での生産回帰(リショアリング)」を推進するため、メキシコやカナダからの輸入品に圧力をかける可能性がある。
ただし、メキシコやカナダは報復「関税」を検討する可能性があり、北米経済圏全体の不安定化を招くリスクがある。
4.対インド・東南アジア関税政策の強化
トランプ大統領は、「アメリカ第一主義」を掲げ、インドや東南アジアの新興国に対しても貿易赤字削減のために、「関税」を利用する可能性がある。
特に、インド・ベトナム・インドネシアとの貿易関係が、ターゲットになると考えられる。
具体的な関税措置の予測
- インドの医薬品・鉄鋼製品への「関税」強化
- ベトナム・タイの繊維製品・電子部品への「関税」導入
- ASEAN諸国との貿易赤字是正を名目とした「関税」圧力
狙いと影響
トランプ大統領は、「中国に代わる製造拠点」として、注目されているインドや東南アジア諸国に対しても、「関税」を使って、アメリカの貿易赤字削減を図る可能性がある。
しかし、これらの国々が、アメリカ市場以外に輸出先を多様化すれば、「関税」戦略の効果は限定的となる可能性もある。
トランプ大統領の関税政策の影響と評価
トランプ大統領が政権を再び握ったことから、トランプ大統領の「関税政策」は、大幅に強化され、米国内外に多大な影響を与えることが予測される。
トランプ大統領は、過去の政権時に「関税は最も美しい言葉」と称し、貿易交渉の手段として活用したが、2025年以降も同様の手法を継続すると考えられる。
ここでは、「関税政策」がアメリカ国内経済に及ぼす影響、貿易相手国の対応、そして長期的な評価について想像してみよう。
1.アメリカ国内経済への影響
トランプ大統領の「関税政策」は、国内産業の保護を目的としているが、企業・消費者・雇用に与える影響は一様ではない。
(1) 企業への影響:製造業の一部回帰とコスト増加
恩恵を受ける産業
鉄鋼、アルミ、自動車、農業など、輸入品と競合するアメリカ国内産業は、恩恵を受ける可能性がある。
特に、鉄鋼業界は2018年の「関税」措置で一時的に業績を回復した例がある。
半導体や電池製造など、政府が補助金と併せて育成しようとしている分野は、保護される可能性が高い。
打撃を受ける産業
- 輸入部品に依存する企業(自動車、電機、精密機器)
例えば、フォードやGMは中国やメキシコから部品を調達しており、「関税」がかかると生産コストが増加。
結果として車両価格が上昇し、販売減少のリスクが高まる。 - 輸出依存の企業(農業、航空産業)
農業分野では、「関税」をかけられた場合、穀物や牛肉の輸出が減少する可能性がある。
2018年には中国がアメリカの大豆に報復「関税」をかけ、農家の打撃が深刻化した。
(2) 消費者への影響:物価上昇と生活コスト増加
輸入品への「関税」は、企業の生産コストを押し上げ、その結果として消費者向けの価格が上昇する。
- 2018年の関税「関税」では、家電、家具、衣料品、自動車など幅広い製品の価格が上昇した。
- 2025年以降も同様に、日用品・食品の価格が高騰するリスクがある。
低所得層ほど影響を受けやすい。
価格上昇による負担は、所得の低い世帯ほど重くなる。
(3) 雇用への影響:製造業回帰と労働市場の混乱
- 国内製造業の雇用増加
一部の業界では、生産回帰による雇用増加が期待される。
ただし、製造業は自動化が進んでおり、過去のように大量の雇用が生まれるとは限らない。 - 他の産業の雇用減少
自動車や小売業界では、コスト増加による人員削減のリスクがある。
貿易相手国の報復関税により、農業・航空業界など輸出依存の業界で、雇用減少の可能性もある。
2.貿易相手国の対応と関係悪化
トランプ大統領の「関税政策」は、アメリカの貿易相手国との関係を、悪化させる可能性が高い。
(1) 中国:貿易戦争の再燃
トランプ大統領が、再び対中「関税」を強化すれば、中国は報復措置としてアメリカ製品(農産物、半導体、自動車など)への「関税」を強化する可能性がある。
半導体やEV関連技術の分野で、米中デカップリング(経済分断)がさらに進む可能性がある。
(2) EU・日本:自動車関税の影響
トランプ大統領が、日本やEUに自動車「関税」を導入した場合、日本やEUもアメリカ製品に報復「関税」を課す可能性が高い。
特に、ドイツや日本の自動車メーカーは影響を受け、日米・米欧関係の緊張が高まる。
(3) メキシコ・カナダ:USMCAの再交渉圧力
メキシコ製品への「関税」を強化し、不法移民対策と絡めてプレッシャーをかける可能性がある。
ただし、メキシコはアメリカ市場への依存度が高いため、譲歩する可能性もある。
3.長期的に見た関税政策の評価
「関税政策」は、短期的には国内製造業を保護し、一部の雇用を創出する可能性があるが、長期的には経済成長を阻害する可能性がある。
(1) 成功といえる点
- 国内製造業の一部回帰を促進
- 中国との経済分断を進め、米国の技術的優位を守る可能性
- 一部の交渉では、他国から譲歩を引き出せる可能性(例:USMCAの再交渉)
(2) 問題点とリスク
- 企業のコスト上昇 → 価格上昇 → 消費低迷 → 経済成長の鈍化
- 貿易相手国との関係悪化 → 世界経済の不安定化
- 企業が「関税」を回避するため、製造拠点を東南アジアなど別の国に移す可能性 → アメリカ国内での生産回帰が思うように進まない
(3) 最終的な評価
トランプ大統領の「関税政策」は、短期的には国内産業を保護し、一定の成果を上げるかもしれない。
しかし、長期的には、貿易摩擦の激化や企業の負担増加による、景気減速のリスクが大きい。
特に、消費者への負担増や、国際関係の悪化を招けば、経済全体の成長を妨げる可能性が高い。
もしトランプ大統領が「関税政策」を継続するならば、その影響を抑えるための補助金政策や、国内企業の競争力強化策が必要になるだろう。
まとめ
トランプ大統領の「関税政策」は、単なる貿易戦略ではなく、武力を使わずに他国と交渉し、国益を確保するための手段であった。
トランプ大統領は、政治家というよりビジネスマンであり、戦争を避けることが最も合理的な選択であると理解していたと思われる。
バイデン政権時代に、ロシア・ウクライナ戦争をはじめとする各地の紛争が勃発したのに対し、トランプ政権時代には、大規模な戦争が抑えられていたことは、「関税」という経済的圧力が武力に勝る交渉ツールであったことを示唆している。
2025年以降、トランプ政権下では、「関税」を交渉の主軸に据えた外交戦略を継続すると考えられる。
これにより、貿易交渉や安全保障において他国に譲歩を迫りつつ、米国の利益を最大化することを狙うだろう。
しかし、「関税政策」には、短期的なメリットと長期的なリスクがある。
国内産業の保護や交渉力の向上といった利点がある一方で、貿易相手国との摩擦や物価上昇、企業の負担増といった負の側面も避けられない。
最終的に、トランプ大統領の「関税外交」が成功するかどうかは、米国内外の経済状況、各国の対応、そしてトランプ大統領自身の政治的手腕にかかっている。
戦争を回避しつつ、「関税」という「武器」を用いた交渉がどこまで成果を上げるのか、2025年以降の世界は、再びトランプ大統領の手腕に注目することになるだろう。
他にも、トランプ大統領の気になる「2025年のキーワード」について記事があるので、チェックしてみてください。