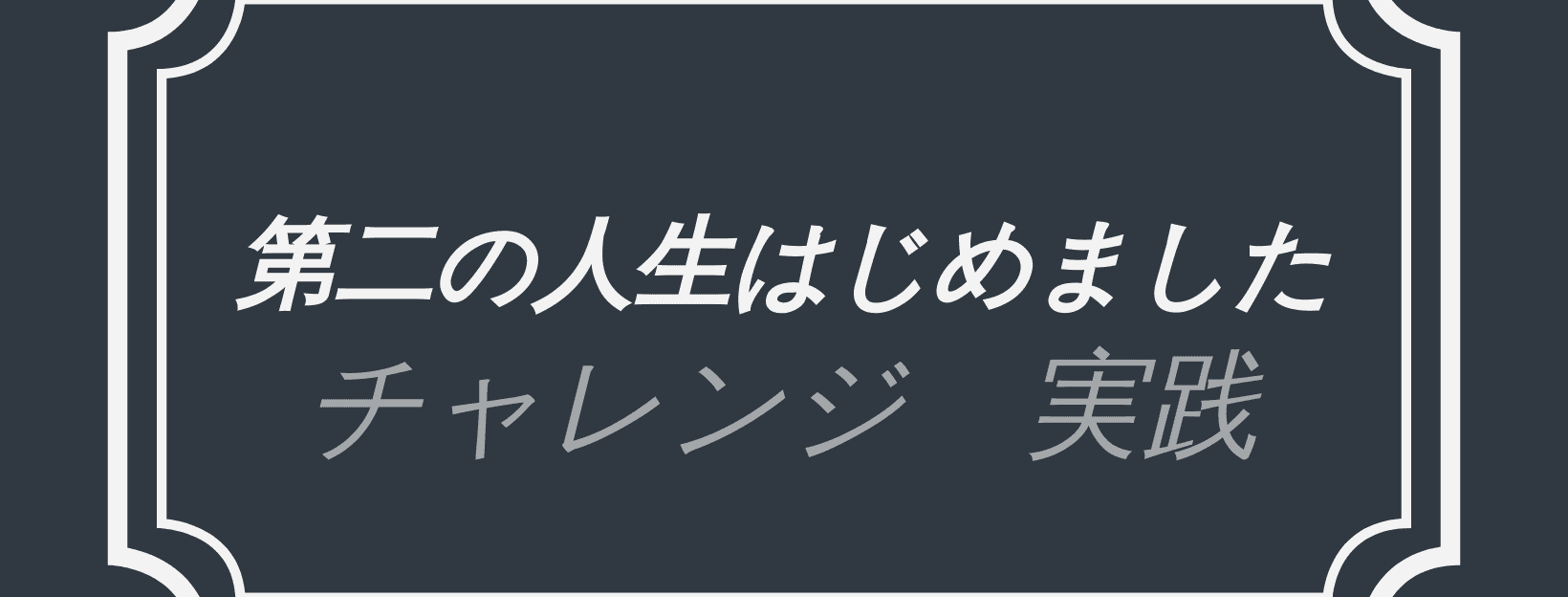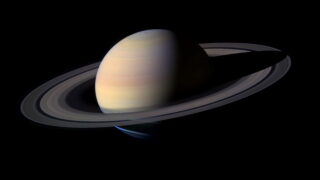年々気候の変化を感じている人も多いと思うが、その気候の変化の影響を受けやすいのは、植物で、我々が特に感じやすいのは、日々の食事に関係のある「野菜類」ではないか。
2024年は、冬は暖かく暖冬で春野菜などの生育が過剰に早く進み、春は気温が下がって桜の開花も各地で遅れ、6月は一転して暑くなり、30℃を超える真夏日が続いた影響で、土の中が高温となり、ニンジンがさけてしまうなど、すでに気象の影響で、様々な野菜類の成長に影響があり、野菜類の価格も高騰している。
また、気温の上昇により病害虫が繁殖するなど、農産物の生産量を低下させてしまうのだが、今年は暖冬の影響で「カメムシ」が大繁殖し、すでに果物などへの果樹被害が報告されている。
野菜の価格高騰は、家計に影響があるので、野菜の安定した供給が求められるところだが、少しづつ工場で栽培された野菜が、市場に出回っていることをこ存じだろうか?
ここでは、「植物工場」による植物の生産で、どの様な植物が栽培されているのか、私たちの食生活にどの様な効果があるのか、見ていきたい。
「植物工場」とは
「植物工場」とは、屋内環境を人工的にテクノロジーを活用し、光や水の量を調整しながら、作物を大量に生産する施設のことで、土を使わず「水耕栽培」のみで育て、水は上水道から引き、気温は空調設備で微調整する。
「植物工場」は、よく見かける「ハウス栽培」や「施設園芸」よりも自然環境(河川水、気温、日照時間、土壌微生物など)への依存割合が低いので、どこでも、例えば「市街地の中心部」にも、工場を建設することが可能となるという。
また、「路地栽培」では、農薬散布等にかかる作業等のコストがかかるのだが、「植物工場」では、その費用や人件費も大きく抑えられるといった大きなメリットが期待される一方で、「植物工場」には、建物の建設などに高額な初期投資が必要になるなど、デメリットもある。
「植物工場」の普及のポイント
日本では、開発、普及が始まったのが1980年代頃で、「人工光型」の植物工場だったとのこと。
開発当初の光源は、高圧ナトリウムランプ(HPSランプ)で生産コストが高く、栽培された野菜の価格も高かったため、販売は一部のデパートや高級スーパーに限定され、購買層も富裕層などに限られていたそう。
それが、近年は「LED光源」の性能が向上し、価格も安価になったため、「垂直農法」(水耕栽培などの装置を垂直方向に積み重ねた面で、野菜や果物などを生産する方法)の「棚型多層栽培システム」が実用化され、施設面積あたりの栽植密度が飛躍的に高まったことと、生産コストも徐々に低下したことで、「植物工場」の普及が一段と加速している。
「植物工場」の普及状況は、技術の進化や需要の高まりにより著しいものがあり、「植物工場」の現在の普及状況についての主なポイントは、以下の通り。
1.技術の高度化
- LED照明: エネルギー効率が高く、特定の波長の光を調整して植物の成長を最適化できるLED照明が広く使用されている。
- 自動化: ロボットやAIを用いた自動化システムが導入され、植え付けから収穫、パッケージングまでのプロセスが効率化されている。
- 環境制御: 温度、湿度、CO2濃度などの環境要素を精密に制御する技術が進化し、最適な成長環境を提供している。
2.市場の拡大
- 都市部での導入: スペースが限られた都市部でも「垂直農法」を活用することで、新鮮な野菜を供給する植物工場が増えている。
- スーパーやレストランとの連携: 大手スーパーやレストランチェーンと提携し、地産地消の形で新鮮な野菜を提供する取り組みが進んでいる。
3.環境への配慮
- 水資源の節約: 循環式水耕栽培技術により、従来の農法に比べて水の使用量を大幅に削減している。
- 農薬の削減: 密閉された環境で育てるため、病害虫の発生が抑えられ、農薬の使用がほとんど不要。
4.新たな作物の試み
- 高付加価値作物: 高栄養価や医薬品原料となる植物の栽培が試みられている。
- 品種改良: 遺伝子編集技術を用いて、栄養価が高く、病気に強い作物の開発が進められている。
「植物工場」の種類
「植物工場」は、現在では、世界的にも研究や導入が進んでいるようで、日本でも先進的な企業が取り組みを開始しているそうだ。
「植物工場」には「人工光型」と「太陽光型」の2種類がありまり、「人工光型」では太陽光は一切入らず、すべてをLEDなどの人工光で栽培するもので、「太陽光型」では、天窓から太陽光を取り入れて栽培しているものを指している。
それぞれの概要は、以下の通り。
【人工光型】
「人工光型」は、人工光源のみを使う植物工場で、太陽光は一切使わないので、人工光源の下で栽培ラックを何段にも積んで栽培することが出来、狭い敷地で多くの作物ができる。
垂直に積み重ねることで栽培面積を広げることができるので、従来の畑や温室栽培で利用する土地面積の「10倍」の収穫を可能にすることが期待されている。
太陽光も遮蔽するので、完全閉鎖系とも呼ばれるが、「人工光源」のみを使ぶんの消費電力がかさみ、電気コストは太陽光型の「約3倍」ともいわれる。
また、栽培棚を積み重ねる構造のため、「背の高い作物の栽培には適してはいない」とのこと。
栽培品目は、リーフレタスやサラダ菜、小松菜、サンチュなどの小型な葉菜類が主流。
【太陽光型】
「太陽光型」は、太陽光をメインで使うため、人工光源のみを使う場合に比べ、消費電力を大幅に削減できる。
人工光源だけではコスト的に見合わない品目の、トマトやイチゴなどの果菜類の栽培が可能になるとのこと。
しかし、太陽光を使うため、天候に左右され、完璧な安定供給ができないのと、太陽光を全ての植物の株に当てる必要があるため、平らで広大な敷地が必要とのこと。
「地球温暖化」が野菜に与える影響
現在、気象変動による影響は、「70品目以上」の農作物に品質低下や収穫量減少が見られると報告されているという。
気象変動による、特に大きな農作物への影響は、「コメ」「ブドウ」「ナシ」「トマト」「ミカン」などがあり、具体的な自然現象としては、「高温、集中豪雨、降水量の増加、干ばつ」など。
農家は、新しい作物栽培や品種改良に挑戦している一方で、気象変動による影響は、現在のところ避けられないのが現実だという。
「地球温暖化」が野菜の生育に影響を与える主な要因
「地球温暖化」が野菜の生育に与える影響については、多くの研究により、いくつかの因果関係が指摘されており、「地球温暖化」が野菜の生育にどのように影響を与えるかについての主な要因は、以下の通り。
1.気温上昇
「地球温暖化」により平均気温が上昇すると、植物の生育期間が短縮される可能性があり、特に温度が極端に高くなると、光合成効率が低下し、成長が阻害されることがある。
2.水ストレス
「地球温暖化」に伴う降水パターンの変化や干ばつの頻度・強度の増加は、野菜の栽培に必要な水分供給を不安定にし、水不足は植物の成長を大きく妨げる要因となる。
3.病害虫の増加
温暖な気候は、病害虫の繁殖を促進し、特に高温多湿の環境では、病原菌や害虫の活動が活発になるため、病害虫の増殖は、野菜の収量や品質が低下するリスクが高まる。
4.CO2濃度の変化
CO2濃度の上昇は、植物の光合成を一時的に促進する効果があるが、他の環境要因との相互作用によっては、逆効果になることもある。
例えば、高温とCO2濃度の同時上昇は、植物の栄養価に悪影響を与えることが報告されている。
5.土壌の劣化
極端な気候条件(例:激しい降雨や干ばつ)は、土壌の浸食や劣化を引き起こし、植物が必要とする栄養素や水分の保持力が低下する。
※これらの要因により、地球温暖化は、野菜の生育に複雑で多面的な影響を与えることが、分かっている。
野菜の種類や、地域の気候条件によって、具体的な影響の程度や形態は異なるものの、全体として農業生産に対するリスクの増大が、予測されている。
「植物工場」の効果
「地球温暖化」による気候変動は、野菜などの農作物の生産に深刻な影響を与える可能性があり、これに対する有効な対策の一つが「植物工場」なのだ。
「植物工場」の主な効果は、以下の通り。
1.安定した生産
「植物工場」では、気温、湿度、光量などの環境要因を人工的に管理でき、外部の天候に依存しないので、年間を通じて安定した生産が可能で、異常気象や季節による影響を受けにくいため、品質の安定化が図れる。
2.効率的な土地利用
「植物工場」は、垂直農業や水耕栽培を採用することで、都市部など限られた土地でも高い生産効率を実現でき、農地不足に悩む地域や都市部でも、新たな農業展開が可能になる。
3.水資源の節約
「植物工場」では、水耕栽培などの技術により、従来の土耕栽培に比べて大幅な水の節約が可能となり、水の再利用システムを組み込むことで、更なる資源の効率化が図れる。
4.農薬の使用削減
「植物工場」は、自然界の環境から切り離された、閉め切られた環境での栽培が主流であり、害虫や病気のリスクが低減されるので、農薬の使用を最小限に抑えることができ、食品の安全性が高まり、消費者にとっても健康的な選択肢となる。
5.地球温暖化対策への貢献
「植物工場」は、効率的なエネルギー利用と、温室ガス排出の削減が可能なシステムを導入することで、地球温暖化対策にも寄与でき、地域ごとの「生産・消費」いわゆる「地産地消」が促進されることで、輸送に伴う「炭素フットプリント」の削減も期待できる。
6.食料安全保障の向上
「植物工場」のような、外部の気候変動に影響されない生産システムは、食料供給の安定性を高め、食料安全保障の強化に貢献できると共に、自給率の向上にもつながり、輸入依存度の低減が期待される。
「植物工場」で栽培される【野菜・果物・キノコ】
「植物工場」で栽培される美味しい野菜には多くの種類があり、その代表的な「野菜や果物とキノコ」は以下の通り。
植物工場で栽培される【野菜】

①レタス
- 栽培が比較的簡単で、生育が早いため、植物工場でよく栽培される野菜の一つ。新鮮でシャキシャキとした食感が特徴。
②バジル
- 高い香りと風味が特徴のハーブで、料理のアクセントとして人気。植物工場では均一な品質のバジルが安定して供給される。
③ルッコラ
- ピリッとした辛味が特徴の葉野菜で、サラダやサンドイッチに使われる。短期間で収穫できるため、常に新鮮なものを提供できる。
④ミズナ(京菜)
- 日本の伝統的な葉野菜で、サラダや鍋料理に使われる。繊細な葉と独特の風味が特徴で、植物工場での栽培に適している。
⑤トマト
- ミニトマトや中玉トマトが特に人気で、甘みと酸味のバランスが取れた美味しいトマトが栽培されている。水耕栽培技術により、一年中安定した品質のトマトを収穫できる。
⑥パクチー(コリアンダー)
- 強い香りと独特の風味が特徴のハーブ。エスニック料理に欠かせない存在で、植物工場で安定して供給されている。
⑦小松菜
- 栄養価が高く、鉄分やカルシウムを豊富に含む葉野菜。スムージーや炒め物に使われることが多く、植物工場で栽培しやすい野菜。
⑧ほうれん草
- ビタミンやミネラルが豊富で、サラダや料理の材料として人気。均一な品質と新鮮さが植物工場の利点。
⑨シソ(大葉)
- 独特の香りと風味を持つ日本のハーブ。刺身の添え物や薬味として使われ、植物工場で安定供給されている。
⑩ミント
- 爽やかな香りが特徴のハーブで、デザートや飲み物のトッピングに使われる。植物工場では高品質のミントが育てられる。
※キャベツや白菜などの「結球(玉形になること)野菜の継続反復栽培はむずかしい」といわれているそうで、現在でもそのハードルは高いとのこと。
結球野菜(キャベツ、レタスなど)が植物工場で栽培されにくい理由
- スペース効率の問題:
- 「結球野菜」は、成長する際に比較的大きなスペースを必要とするが、植物工場は通常、垂直農法や密集した配置でスペースを有効に活用することが求められる。結球野菜はこれに適していない。
- 成長期間の長さ:
- 「結球野菜」は、収穫までの期間が長いことが多く、そのため回転率が低くなる。植物工場では、高頻度で収穫できる葉物野菜やハーブが優先されることが多くなる。
- 栽培条件の複雑さ:
- 「結球野菜」は、結球のため、特定の温度、湿度、光条件を必要とし、これらの条件を管理するのが難しい場合がある。植物工場では、均一な環境で大量生産が求められるため、個別の管理が難しい結球野菜は適していない。
- 経済効率の問題:
- 「結球野菜」は、市場価格が比較的低く、植物工場での生産コストを回収しにくい場合がある。葉物野菜やハーブの方が高付加価値を持ち、短期間で収穫できるため、経済的に有利となる。
- 品質のばらつき:
- 「結球野菜」は、結球の状態や大きさにばらつきが出やすく、均一な品質を求められる市場では不利になる。植物工場では、均一な品質を提供することが重要視される。
※これらの理由から、植物工場では「結球野菜」よりも葉物野菜やハーブの栽培が優先されることが多く、技術の進歩により、今後これらの課題が解決される可能性もある。
根菜類も、水耕栽培ではほとんどうまくいかないので、「根菜は水耕栽培で栽培ができない」というよりも、水耕栽培には適しない区分の野菜である、ということができるのだそう。
植物工場で栽培される【果物】

- イチゴ
- 甘くてジューシーなイチゴは、植物工場での栽培が盛んで、温度や湿度をコントロールすることで、一年中安定して高品質なイチゴが収穫できる。
- ブルーベリー
- 小粒で甘酸っぱいブルーベリーは、抗酸化作用が高く、健康に良い果物として人気があり、植物工場での栽培が進んでいる。
- ラズベリー
- フレッシュな酸味と甘みが特徴のラズベリーは、栽培環境を最適化することで、植物工場でも高品質な果実が得られる。
- ブラックベリー
- 濃厚な味わいのブラックベリーは、デザートやジャムに使われることが多く、植物工場での栽培が可能。
- グーズベリー
- 甘酸っぱい味わいが特徴のグーズベリーは、ビタミンCが豊富で、植物工場でも栽培されている。
- トマト(フルーツトマト)
- フルーツトマトは、糖度が高く、フルーツのような甘さがあり、植物工場では、一年中安定した品質のトマトが収穫できる。
- パッションフルーツ
- 香り高く、甘酸っぱい味わいが特徴のパッションフルーツは、植物工場での栽培が進んでいる。
- フィグ(イチジク)
- 甘くて濃厚な味わいが特徴のフィグ(イチジク)は、植物工場での栽培により、品質を安定させることができる。
- クランベリー
- 酸味が強く、健康効果の高いクランベリーは、植物工場での栽培が進んでおり、フレッシュなものが手に入る。
- メロン(小型品種)
- 甘くてジューシーな小型のメロンは、植物工場では、温度と湿度の管理が容易なため、高品質なメロンの栽培が可能。
※これらの果物は、植物工場の高度な環境制御と栽培技術により、常に高品質で新鮮なものが提供されている。
植物工場で栽培される【キノコ】

①エリンギ
- 太くて肉厚な傘と茎が特徴。歯ごたえが良く、炒め物やグリル、煮物など様々な料理に使われる。
②シメジ
- 小さな傘と細長い茎が特徴。風味が豊かで、炒め物や汁物、和え物に使われることが多い。
③マイタケ
- 独特の風味と歯ごたえが特徴。炒め物や煮物、炊き込みご飯などに使われ、栄養価も高い。
④ブナピー(白シメジ)
- 真っ白な見た目が特徴のシメジの一種。風味がマイルドで、サラダや炒め物、スープに使われる。
⑤ナメコ
- 小さな傘とぬるぬるとした触感が特徴。味噌汁や煮物、炒め物に使われ、特に日本料理で人気がある。
⑥エノキタケ
- 細長い茎と小さな傘が特徴。しゃきしゃきとした食感で、鍋料理や炒め物、サラダに使われる。
⑦しいたけ
- 傘が大きく、肉厚なきのこ。風味が強く、グリルや煮物、炒め物、天ぷらに使われる。
⑧ヒラタケ
- 傘が広く、平らで、柔らかい食感が特徴。炒め物や煮物、スープに使われる。
⑨タモギタケ
- 黄色い傘が特徴で、独特の風味がある。炒め物やスープ、リゾットなどに使われる。
⑩マッシュルーム
- 白色やブラウンの種類があり、肉厚でジューシーな食感。サラダ、炒め物、グリル、パスタなど幅広い料理に使われる。
⑪キクラゲ
- 耳のような形状が特徴で、色は茶色から黒色で、半透明のものもあり、食感はコリコリとした独特の歯ごたえがある。スープ、炒め物、サラダ、春巻き、炒麺などに使われ、特に中華料理では欠かせない食材。
※「マツタケ」や「ホンシメジ」「トリュフ」などの「菌根性キノコ」は、生きたアカマツなどの樹木の根に、「菌根」というものを作り、樹木と共生していて、この様な「菌根性キノコ」は、人工栽培が不可能とされてきたが、「ホンシメジ」では、いくつかの機関で人工栽培に成功したという報告もあるそう。
まとめ
「植物工場」は、「地球温暖化」による気候変動の影響を受けにくく、安定した食料生産を実現するための有効な手段となり、「効率的な資源利用」「農薬削減」「食料安全保障の向上」など多岐にわたるメリットを生かし、今後ますます持続可能な農業の発展に寄与するだろう。
「植物工場」の日本での研究は、1950年代に始まり、2000年代初頭には実用化が加速、近年ではロボットやAIによる自動的な生産管理や、LEDライトの省電力化などの技術革新による生産コストの削減、小ぶりな野菜、清潔な野菜への嗜好の高まりなどにより、今や「植物工場」で生産された野菜は、日常的に食卓へ上るものになっている。
現状では、「植物工場」で生産できる野菜の品目は、葉物野菜と一部の果菜類に限られているが、今年の様に、地球環境が全世界的に変化してくると、多くの食材を国外からの輸入に頼っている日本では、安定した食材の確保が難しくなってくると思われる。
今後も「植物工場」で「無農薬で高品質で安価」に栽培された野菜の流通が進めば、一定の需要を見込むことが出来るかもしれない。